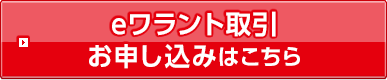マーケット > レポート > eワラントを極める! > 21世紀の新投資格言18選
21世紀の新投資格言18選
2015/2/23
各種メディアの相場解説やSNSの投稿から投資勉強会まで、数多くの投資格言が日常的に使われています。しかし、それが江戸時代の米相場や高度成長期の株式相場に由来するものであったりすると、現在の世界情勢にそぐわなかったり、投資のプロまでが誤用してしまったりします。そこで、過去の相場と現在は何がどう変わっているのかを踏まえて、21世紀にふさわしい投資格言を考えてみました。
【キャンペーン】 4/10(金)まで (抽選で最大600名様に当たる)
eワラントで書籍や現金3,000円が当たる!?キャンペーン中
状況が異なっていて使えないものが増えた投資格言
日本の投資格言には江戸時代に行われていた米先物取引に由来するものが多くあります。お米の豊作・不作は天候に左右されますし、当然ながら夏から秋にかけて供給が増えます。このため、「節分天井 彼岸底」というように2月の節分の頃に先行きが分からない事もあって米の先物価格は高値となりやすく、供給が一気に増える9月の秋の彼岸には安くなります。これが米相場の格言である事を考えれば分かるはずなのですが、株式関係者でさえ、「2月初めに最高値、そのほんの2ヶ月弱後には最安値」と勘違いしている方が多くいます。まして、FXになるとあくまで通貨間の交換比率なので、「何時ごろ何かが高い・安い」という投資格言の言い回しでさえ当てはまらなくなっています。
「電気が消えると お化けが出る」といわれたのは高度成長期の頃で、“家電メーカーを中心にした電機株が下がると相場全体に閑古鳥が鳴く”、あるいは“電機株が下がると化学・薬品株が上がる”という意味です。言うまでもなく、当時の花形銘柄は現在事業の建て直しに苦戦しているところも多く、「電気がいつ点灯したのか消えたのか、お化けが出たのかどうか」もはっきりしません。 また、経済のグローバル化・一体化が進み、多国籍企業の存在感が増すとともに各国の株式相場の相関が極めて高くなっています。にもかかわらず、欧米の古くからある「卵は一つの篭(かご)に盛るな」という格言を、分散投資万能の裏付けのように使う専門家も散見されます。ITバブルの崩壊やリーマンショックのような暴落時には全部同時に落ちるので、今では「卵を盛った籠は全部まとめて落ちる」のです。
さらに、少子高齢化によって経済規模が縮小してきた日本の失われた20年のような事態がかつては無かったので「二番底は黙って買え」などと言われていました。しかし、もし20年間日本株への投資を続けていたら、1995年の二番底でも、1998年の三番底、2003年の四番底、2009年の五番底でも1989年末の高値に戻る気配もなく、ようやく2012年の六番底で長期トレンドが反転するかどうかという瀬戸際です。
21世紀の新投資格言18選はコレだ!
上記のような時代背景の変化や、格言のモトとなった投資対象と株式やFXとの違いに加えて、投資家の均質化、個人投資家によるネットでの株式やFX取引の急増、システム売買の普及、HFT(高頻度取引)の取引シェア拡大、投資のアノマリーや行動経済学に関する研究の進展なども、株式、商品や外国為替相場の値動きに影響を与えるようになりました。
これらを踏まえた、新作の21世紀の投資に有益と思われる投資格言が下記の18個です。
◎相場の大きな流れをみるもの
1.「利上げは ガラまで 止まらない」
FRBも日銀も過去に景気を冷やそうと金融引き締めを行った際に、やりすぎてガラ(大暴落)を引き起こしてしまったことが何回もあります。中央銀行の利上げが始まったら、大暴落まで止まらないものだと覚えておく必要があるでしょう。
2.「泣く子とイエレンには勝てぬ」
中央銀行の中でも基軸通貨国である米国のFRB議長の発言は強力です。戦っても(逆方向にポジションをとっても)勝ち目は少ないことを肝に銘じておきましょう。投資は相手を選ぶ事が大事です。
3.「富める者 ますます富むのは 昔から」
フランスの経済学者ピケティ氏の格差拡大の議論がもてはやされていますが、「富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなる」のは旧約聖書の時代から変わっていません。現実を嘆いても何も変わりません。そこから何を学ぶか、どう行動するかが重要なのも、いつの時代も同じです。
4.「継続はリスクなり」
7年から10年毎に大きな市場ショックがくるとすれば、のんべんだらりと投資ポジションを採り続けていることは、大凶が出るまでおみくじを買い続けているようなものです。
5.「ご機嫌に 長く続けて 泣きを見る」
毎月積み立てによる長期分散投資はあくまで数十年前までの米国株の研究から作られた投資理論に基づいています。日本だけでなく、これからは中国や韓国、欧州まで人口が減少していく縮小経済は想定されていません。
6.「4度目の バブルもやっぱり 今度は違う」
日本で“バブル”と言う言葉が広く使われるようになったのは、1980年代末から1990年初めのバブル景気の頃からです。ITバブル、サブプライムバブルと数えるなら、アベノミクスは4度目のバブルともいえそうです。そして、今回も「バブルではない」と言う言葉が聞こえ始めてきました…
7.「月を笑えば 相場に笑われる」
投資経験が浅い投資家や個別株アナリストは、月足(つきあし)のチャートよりも日足や週足、短期トレーダーなら分足(ふんあし)しか見ない方も多いようです。「そんな昔のことを気にしてたら、相場についていけないよ」などと言っていると、相場の天底を見誤り、後で痛い目をみることがあります。月足は大事です。
◎投資タイミングを示唆するもの
8.「大儲けと大損の後は休め」
大儲けすると気が大きくなり、ついつい直ぐにもっと大きなポジションを採ってしまいがちです。経験則で言えば、たいていこれが大失敗につながっています。逆に大損すると、それを取り返そうと無謀な投機に走りがちで、損失を拡大することが多いものです。大儲けした時と大損した時は少し時間を空けて頭を冷やしましょう。
9.「全勝は売り」
一部が勝って、一部が負けて、全体としてプラスとなっているうちは良いのですが、保有株全てに加えて、FXや商品先物のポジションまですべて勝っている状況は異常と認識すべきです。
サブプライムバブル崩壊直前に売り抜けた巨大ファンドや投資銀行はこの“勝ちすぎ”を売りシグナルとしていたようです。
10.「下げ相場 もうそろそろが 命取り」
古くからの投資格言に「落ちるナイフを拾うな」というものがあります。サブプライムバブルが崩壊し始めた頃に「うちは床に落ちて刺さったナイフを拾っているから大丈夫」といって大損した某機関投資家もいます。
11.「株主優待銘柄は優待確定日に売れ」
個人投資家に人気がある株主優待銘柄は、目先の数千円の物品をもらうのではなく、権利確定日に売り払う、あるいはショートすることが有効と考えられます。
12.「ストップロスのルールを変えたらしまい」
損を小さく抑える手法で有効なもののひとつが逆指値の損切り注文です。ところが実際に下がり始めると、いろいろと理由を見つけてストップロス注文が出せないものです。このルールを変えることは多くの場合売りシグナルなので、諦めてすぐに手仕舞いましょう。
13.「PERが下がったら気をつけろ」
相場の天井付近では企業業績は好調となる一方、株価は伸び悩みます。このためPERが下がるので、これを割安と勘違いしてはいけません。
14.「慌てるな 儲け損ねは 損じゃない」
他人が大儲けするのを見聞きすると、投資機会を逃した自分だけが損をした気になるものです。
こうして投資ビギナーがこぞって参戦すると相場の天井になります。実際は、儲け損なっても1銭も損をしていないので、錯覚を起こさないようにしましょう。
◎投資テクニックに関するもの
15.「地図と四季報は古い方がいい」
不動産を購入する時は古地図を調べ、そこが沼や池だったのか、崩れやすい地形を示唆する地名ではなかったか、という点を調べる事が極めて有益です。同様に株式投資でも、古い四季報で過去どういった分野で注目されていたのが、過去の不況で大赤字になっていないか、業績の下方修正を小出しにしていないどうか、などを見て投資対象を絞り込んだほうが賢明です。
16.「にやにや5割、だろだろ8割」
自分の含み益を眺めてニヤニヤし出したらポジションを半分手仕舞い、思わず誰かに自慢して「これ買ってて正解だろ〜」などと言ってしまうようならポジションの8割を手仕舞った方がよさそうです…
17.「売り時を考えて買うべし」
買いポジションを採る時は天まで上がると想像しがちです。売却する時期や目標価格の目安もない投資では、ちょっとの利益で売ってしまったり、欲張り過ぎて売り時を逃したりすることが多くなります。「この株は〇〇円くらいであるべき」、「GWまでには売ろう」というような大まかな目安でも意外に役に立ちます。
18.「宝を掘り出し、穴に落ちる」
もの凄く“割安に放置”されている銘柄を見つけて、「どうしてみんなはバカなんだろう」と大金をつぎ込んだら、業績が急低下して大損した…ということがあります。「人の逆」が大きなリターンを得るポイントではありますが、自分だけ何かを見逃していないか十分に調査する必要があります。
(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)
eワラント証券 チーフ・オペレーティング・オフィサー 土居雅紹(どい まさつぐ)
eワラントの関連コンテンツ
ちょっとe(イー)銘柄の見つけかた
春節到来!インバウンド関連銘柄に再注目!
ご注意事項
- eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報はホームページの「手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。
- 本資料は情報の提供を目的としており、本資料によって何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社は本資料が正確、完全あるいは/且つ最新のものである事を表明するものではなく、またその責任も負いません。尚、当社及び当社の関連会社、役員、社員その他本資料の作成に携わった関係者が本資料に記された企業の証券または(オプションなどの)派生商品の買い持ちや売り持ち、及び売買を時として行うことがあり得ます。本資料に掲載されている内容の著作権は、原則としてeワラント証券に帰属します。事前に当社の書面による許可なく、本文の一部または全部を第三者へ再配布することを禁じます。
- eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
- ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
- トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
- SBI証券におけるカバードワラント取引手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。
商号等 / eワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会 / 日本証券業協会
提供:eワラント証券