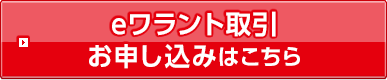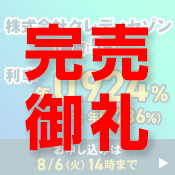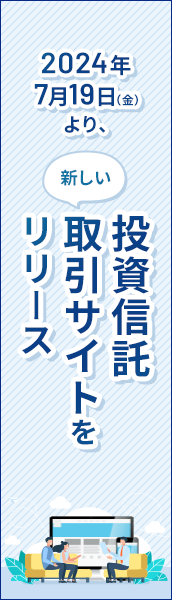2008年以降の大規模な量的金融緩和政策(日本は2013年から)で押し上げられた各国の株価が、中国の人民元切り下げをきっかけに大幅に下落する結果となりました。各国政府の対応で落ちつきを取り戻してきましたが、ここでやれやれと一息ついてしまうのはまだ早いかもしれません。現状を俯瞰してみると、これが「量的緩和バブル」の終わりのはじまりである可能性も高そうです。現在までの株高の背景と過去の巨大バブル時の値動きパターンなどから、暴落への対応を考えてみましょう。
eワラントとは?
そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。
近年の世界的な株高は「量的緩和バブル」?
図1は米日欧のベースマネー(市中に出回る紙幣と金融機関が中央銀行に預けているお金の合計=中央銀行が直接コントロールできるお金)と株価を重ねてみたものです。
これを見ると、ベースマネーが増えると株価が上がるという関係が特に日米で顕著に見てとれます。米国ではリーマンショック直後の2008年以降、「お金を空からばら撒けば景気が良くなる」という発言から“ヘリコプターベン”と呼ばれたバーナンキFRB議長の下、積極的にベースマネーを増やす量的緩和が行われてきました。その伸びが止まった2014年末頃から米国株も伸び悩んでいます。日本は4年遅れでしたが、量的緩和を主張するアベノミクスが始まってから株価が急伸しました。欧州はユーロ財政危機とドイツ一人勝ちで周辺国は不況に苦しむという偏りがあるものの、やはり量的緩和に株価が支えられていました。2012年に一旦ベースマネーを減らし始めるとドイツ株は伸び悩み、周辺国の不況は深刻になりました。それが2014年末に国債買い入れによる量的緩和再開を決めると、再び株価は急上昇しました。
日米欧の株高が量的緩和によるものが大きいとすれば、これは「量的緩和バブル」といってよい状況です。本年中に米国で利上げが行われると株価急落が懸念されているのも、ジャブジャブマネーでかさ上げされた株価という背景があるからです。日欧はしばらく株式相場にベースマネーという薪をくべ続けると予想されます。しかし、米国のベースマネー減少が顕著になればいよいよ量的緩和バブルの終焉が近づくことになりそうです。このため、しばらくは米国のベースマネーの変化に要注意といえます。
図1:米日欧のベースマネーと株価
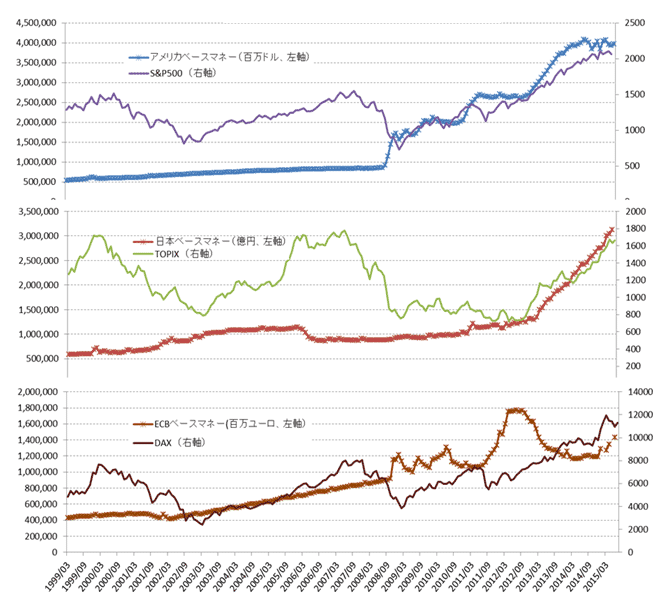
※FRB、日本銀行、ECB、ロイターデータよりeワラント証券が作成
バフェット指標で再確認;今回の急落でも調整は不十分
図2はGDPと株式の時価総額を比較して相場水準を探るバフェット指標の推移です。2014年末の時点で、米国株の時価総額とGDPの乖離は不動産中心のバブルであったサブプライムバブルを大きく上回っています。また、株式中心のバブルであったITバブルのピークの水準に近いところまで株式が買い進まれています(図中赤矢印)。
これが今回(2015年8月)の“中国人民元切り下げショック”後(図中黄矢印)でも、GDPを上回る水準にあり、まだ過熱感は消えていません。
ちなみに、ITバブル崩壊後の大幅調整でも、2008年の世界金融危機(図中緑矢印)でも、株価はGDPを大きく下回る水準まで下げる結果になっています。この意味では、今回の下落は過熱感を消すには「お話にならないぐらい足りない」調整に過ぎないといえます。
図2:米国株をバフェット指標で再点検すると
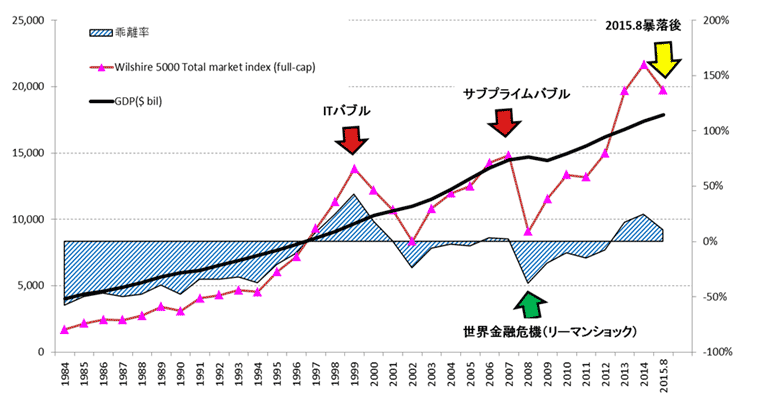
※米国商務省、ロイターデータよりeワラント証券が作成
過去の巨大バブルと比べてみたら...「終りのはじまり」はインテリトラップに注意!
図3は過去の大型バブル崩壊時にNYダウがどういう値動きをしていたか、今回の“量的緩和バブル”がピークアウトしたと仮定して重ねてみたものです(今回は水色線)。
図から分かるのは、やはり「今回の下げは全く下げの部類に入らないほど小さい」ということです。また、大恐慌、ITバブル、サブプライムバブルなどをみると、天井圏で今回程度のジェットコースター相場を繰り返しながら下げトレンドとなったり、その後もっと大きな下落が続いたりしています。そう考えると、やはり今回の世界的な株価調整は「量的緩和バブルの終わりのはじまり」で、仮に持ち直しても数ヶ月から1-2年以内にドッカーンと来る可能性は否定できません。
なお、投資格言に「落ちるナイフを掴むな」というものがありますが、まさにこれが大暴落の初期に最も注意すべきことです。拙著「勝ち抜け!サバイバル投資術」や「最強の『先読み』投資メソッド」ではこの時期を「インテリトラップ」と呼んでいます。これは暴落直前の企業業績が急激に悪化する直前では、多くの企業の業績予想は好況が続く前提のままです。一方株価は景気に半年程度先行することが多いので、先に急落します。この結果、PER(株価収益率)などの指標ではほとんどの株式が超割安に見えてしまうのです。頭でっかちのインテリ投資家ほど(プロも含めて)このトラップに騙されて、落ち始めた株式を購入してその後の大暴落で痛い目をみやすいので、「インテリトラップ」(別名「インテリホイホイ」)なのです。
図3:過去の巨大バブルにおけるNYダウの値動き
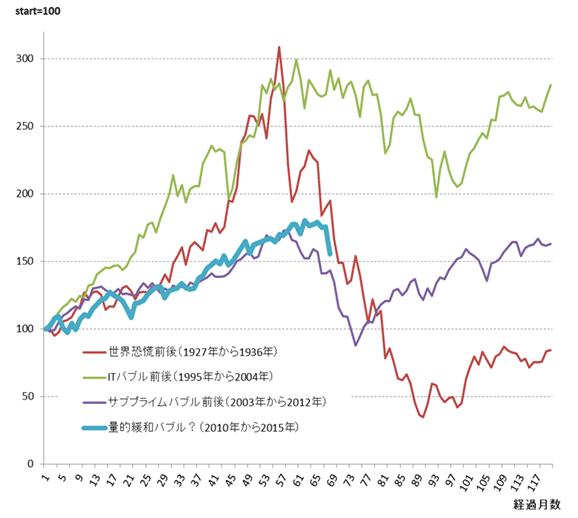
※ロイターデータよりeワラント証券が作成
ここからの更なる暴落がありそうだと思ったら
相場全体の株価水準は四季の気温の変化に似たところがあります。春先に大雪があっても気温は上昇トレンドなので夏になり、それが冷夏だったり酷暑だったりしても、やはり秋が来て冬になります。つまり、上がったものは下がり、下がったものは上がるということです。また、機関投資家並みの資金量を持つごく一部の方を除けば、個人投資家はプライステーカーであって、大声を出しても走り回っても株価は動きません。
また、周期的にやってくる暴落は「パソコンの作業中にデータが消し飛んでしまった状態」に似た面もあります。手をつくせば回復できることもありますが、何をどうやってもダメなこともあります。そんな時は嘆いていても何の役にも立たず時間の無駄なので、割り切って粛々とできることから手をつけるしかありません。もちろんをパソコンも相場もクラッシュの可能性を予見して、しっかり準備(パソコンならデータバックアップ、投資ならプット買いやキャッシュ管理)してあれば損害は最小限ですみます。
そこで、株式暴落時の心得と具体策をまとめてみました。
・相場勘だけに頼った投資は行わない(あるいは全資産の10%以下に限定する)
・先進国株式間の分散投資ではなく、投資戦略の分散によるリスク低減を目指す
・PERが数百倍にもなっている株、株価が100円以下の株は原則として買わない
・暴落に最も弱い上場株価指数オプションのプット売り戦略は避ける
・FXの資源国通貨のレバレッジは数倍以下にする
・(現在のように危なそうな時は)キャッシュ比率は30%以上にしておく
・人口動態で長期的に不利な中国、韓国、日本、タイ、欧州への投資割合を減らす
・インバウンド関連銘柄や中国依存度の高い国内株式の保有を減らす
・韓国200種株価指数、ハンセンH株指数のプット、TOPIXプット、日経マイナス3倍レバレッジトラッカーなどを、アノマリーで危険度が上がる5月から10月まで保有してみる
・株式だけでなく、eワラント、ニアピン、レバレッジトラッカー、各種ETF、ミニ先物などの商品知識を増やし、どういう局面で何が夜何時まで売買できるか知っておく
・まず全ポジションの時価を把握する
・投げるか、耐えられるか、今後の最悪の事態を想定して判断する
・流動性が枯れてしまった資産は諦めて数年待つ覚悟をする
・売却するなら、成り行きではなく指値で処分する(カモネギにならないため)
・巷の楽観論と悲観論を吟味し、少数派の意見をより重視する
・十分考えつくしたら、くよくよしないで気分転換する
・損失が大きかったら、新しいポジションを採らずにしばらく休む
・新しい投資戦略を採用する場合は、まず少額から試す
・現実的な買い指値に加えて、思いっきり下の買い指値も入れてみる
・損失を短期間で取り返そうとして過大なポジションは決して採らない
・VIX指数ETFは使わない(急落時には既に高騰していて、その後急落することが多い)
・S&P VIX(米国株の恐怖指数)、PCレシオ、信用取引評価損益率などで大底を探る
・各国政府の大規模対策が出てもすぐに飛びつかない(3ヶ月から半年待つ)
・内閣支持率が急上昇するようなら迷わず買う
(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)
eワラント証券 チーフ・オペレーティング・オフィサー 土居雅紹(どい まさつぐ)
eワラントの関連コンテンツ
ちょっとe(イー)銘柄の見つけかた