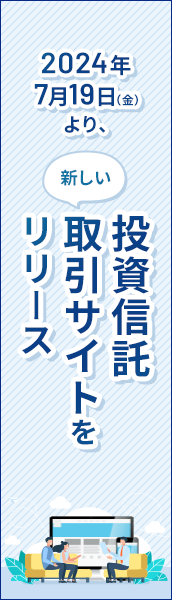�u���̌o�ς͈������Ă��Ȃ��̂ŁA���݂̊��������͊����v
�u���̊��������͎��̌o�ςƂ̊W�����Ⴂ�v
�u�t�@���_�����^���Y����l���Ė{�i�I�ȃn�[�h�����f���O�͂Ȃ��v
2016�N1����������n�܂������E�I�Ȋ��������ŁA�����������s��W�҂̃R�����g���U������܂����B�������A�u�����ǂ����ŕ������悤�ȁc�v�Ƃ��������������ڂ���ꂽ�������邱�Ƃł��傤�B�����ŁA�ߋ��ɗL���҂̌o�ς�i�C�ɑ���R���Z���T�X���ǂ��ł������̂��A�O��̃T�u�v���C���o�u������O����̓��{��s���܂Ƃ߂Ă���u�W�]���|�[�g�v�ŒT���Ă݂�Ɓc
e�������g�Ƃ́H
���������������g���ĂȂɁH3,000�~���̏��z����n�߂���ue�������g�̖��́v�����Љ�����܂��B
�u�C�����悤�@�R���Z���T�X�ł́@�����x���v
�}1�̓T�u�v���C���o�u�����ނ��ނ��Ƒ傫���Ȃ��Ă���2003�N����̓��o���ρi�����j�̐��ڂɁA��v�ǖʂɂ�����u����W�]���|�[�g�̌i�C���ʂ��v�̃R�����g�����Ă��Ă͂߂����̂ł��B
�}1�F���o���ρi�����j�Ɠ���E���{�v�l�R�����g
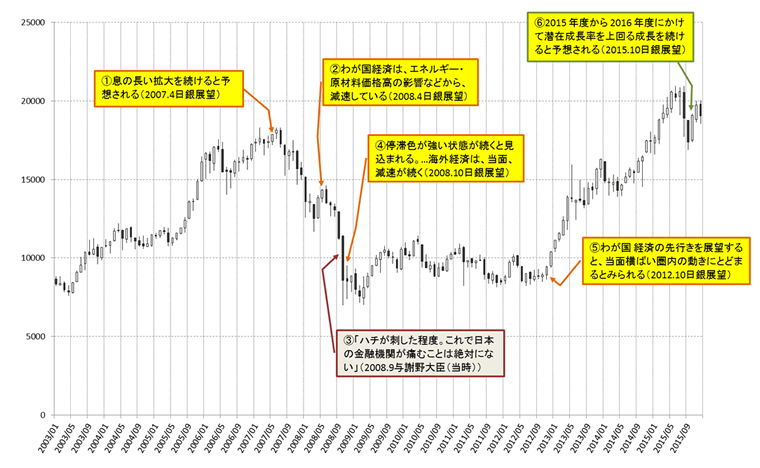
�����C�^�[�f�[�^�A���⎑�����e�������g�،����쐬
2000�N�ȍ~�̕č��́uIT�o�u��������Z��o�u���n�o�ŏ��낤�Ƃ����v�Ƃ����قǂŁA���X�N�������l�ɑ���Z��[���i�T�u�v���C���E���[���j�𐭕{���ϋɓI�Ɏx�����Ă��܂����B���̌��ʁAFRB�̋��Z�ɘa��������ĕč��s���Y�𒆐S�Ƃ������E�I�ȋ���o�u�����������܂����B2006�N�ɂ͊��ɕč��̕s���Y���i�̓s�[�N�A�E�g���Ă��܂������A�����s��͈ˑR�Ƃ��č��l���ɂ���A�č����O�̃G�R�m�~�X�g���u�č��o�ς̃n�[�h�����f�B���O�͖����v�Ƃ����ӌ����x�z�I�ł����B�������ɂ��ꂸ�A2007�N4���̓���W�]���|�[�g�͂��Ȃ�y�ϓI�Ȃ��̂ł����i�}���R�����g�@�j�B
�u��s��2007�N�x����2008�N�x��W�]����ƁA���Y�E�����E�x�o�̍D�z���J�j�Y�����ێ��������ƂŁA���̒����g��𑱂���Ɨ\�z�����B�c�č��ł́A�Z��s��̒����͑����Ă��邪�A����܂ł̂Ƃ���A�l��������ɐ��ڂ���ȂǁA�o�ςɍL�͂ȉe�����y�ڂ��Ă��Ȃ��B�܂��A�ݔ������́A���̂Ƃ����s�w�W�̈ꕔ���ア�����ƂȂ��Ă��邪�A�������̊�Ǝ��v��w�i�ɁA�ɂ₩�ȑ�������ێ������Ƃ݂���B�v�i2007�N4�� ����W�]���|�[�g�j
2007�N7���ɂ͕�BNP�p���o��s�n�̃T�u�v���C�����ɓ�������w�b�W�t�@���h���j�]���A2008�N3���ɂ͖��哊����s�x�A�E�X�^�[���Y�������I�ɔj�]���AJP�����K���E�`�F�[�X�ɋ~�ύ�������܂����B2008�N4���̓���W�]���|�[�g�i�}���R�����g�A�j���o���̂́A���o���ς�2008�N3����12000�~���t���A4���ɂ悤�₭13000�~��ɉ������Ɍ��������̍��ł����B���̎��_�ł悤�₭�i�C��ނ�F�߂Ă͂��܂����A�i�C�����̌����́u�G�l���M�[���i�̍����v�Ƃ��Ă����悤�ł��B
�u�킪���o�ς́A�G�l���M�[�E���ޗ����i���̉e���Ȃǂ���A�������Ă���B�O��i2007�N10���j�́u�o�ρE������̓W�]�v�i�W�]���|�[�g�j�Ŏ��������ʂ��Ɣ�ׂ�ƁA�Z�����ݔ������͉��U�ꂽ����A�A�o����U�ꂽ���߁A2007�N�x�̐������́A���ʂ��ɊT�ˉ����āA���ݐ��������݂ƂȂ����Ƃ݂���v�i2008�N4�� ����W�]���|�[�g�j
2008�N9���ɂ̓��[�}���E�V���b�N���������A�N�̖ڂŌ��Ă���@�I�ȏł����B�s��W�҂́u����ԈႤ�Ɛ��E���Q���݂̑�s���ɂȂ�v�Ƃ�����@��������Ă��܂������A���{�̐��{�v�l�͑S���قȂ鐢�E�ρi����ρH�j�������A�y�ϓI�������悤�ł��c�i�}���R�����g�B�j
����W�]���|�[�g�ŁA�u���Ȃ�̕s�����A���������v�Ƃ�����|�̋L�ڂƂȂ�̂�2008�N10���i�}���R�����g�C�j�ł��B
�u��s�� 2008�N�x�㔼���� 2010�N�x��W�]����ƁA2009�N�x�����܂ł́A��ؐF��������Ԃ������ƌ����܂��B�c�C�O�o�ς́A���ʁA�����������Ƃ݂���B�č��ł́A�Z��i�̑啝�ȉ����������Ă���A���Z�@�ւ̑ݏo�p�������i�����Ă���B�v�i2008�N10���@����W�]���|�[�g�j
���ɁA����W�]���|�[�g���u���҂̃R���Z���T�X�v���邢�́u�s���S���҂̌����v�ł���Ƃ���Ȃ�A�N���ǂ����Ă��������ꂪ�N���b�V��������ŁA���o�ς���@�I�ɂȂ��Ă���łȂ��ƁA���������͖\����s����F�߂Ȃ��Ƃ��������ł��B
����̑告��ł������H
�����Đ}1��2012�N�ȍ~�́A����̃A�x�m�~�N�X����Ɋւ��镔����2012�N10���̊�������}�����O�ł́A�u���҂̃R���Z���T�X�v���ǂ��ɂ������̂��A����������W�]���|�[�g�Ō��Ă݂܂��傤�i�}���R�����g�D�j�B
�u�킪���o�ς̐�s����W�]����ƁA���ʉ��������̓����ɂƂǂ܂�Ƃ݂������A�������v���S�̂Ƃ��Ă݂�Βꌘ�����ێ����A�C�O�o�ς�����������Ԃ��玟��ɒE���Ă����ɂ�āA�ɂ₩�ȉo�H�ɕ����Ă����ƍl������B���̊ԁA��Ƃɂ����O�̐��ݎ��v�̌@��N������{�ɂ�鐬���헪�̎��s�Ȃǐ����͋����ւ̎��g�݂̐��ʂ����X�ɂ�����A��Ƃ�ƌv�̒������I�Ȑ������҂����ʂ����ԏI�Ղɂ����Ċɂ₩�Ȃ��獂�܂��Ă������ƂŁA�i�C�̎������������Ă����Ƒz�肵�Ă���B�v�i2012.10����W�]���|�[�g�j
���������ƁA�o�ό��ʂ��́u���ʉ����v�Ƃ��Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA�u�C�O�o�ς�����������Ԃ��玟��ɒE���Ă����ɂ�āc�v�Ƃ��Ă��܂����A�����̓���̉~�����F����̂����œ��{�����[�}���V���b�N��̐��E�̕s�������Ɉ��������ʁA���Ē��̌o�ς͂Ƃ����ɉ��Ă��܂����B2012�N11�����ɏO�c�@���U�����܂����Ƃ��납��A�x�m�~�N�X���ꂪ�n�܂�܂����A��ɂȂ��āu�A�x�m�~�N�X�������Ă����{�o�ς͎����̓r��ɂ������v�Ƃ����g�L���ҁh���U�����ꂽ�̂ŁA�����ł��u���҂̃R���Z���T�X�v����t���ł���ƌ�����ł��傤�B
2015�N�ɂ́A�������͂��߂Ƃ���R���f�B�e�B���i�̉����������A���������}�����A�l�����V���b�N������A�W�����N�ɓ�������w�b�W�t�@���h���j�]���Ă��܂��B����ł��A���߂�2015�N10���̓���W�]�ł��A�ǂ����Ō����悤�Ȋy�ϓI�ȕ\��������ł��܂����i�}���R�����g�E�j�B
�u2017�N�x�܂ł̓��{�o�ς�W�]����ƁA2015�N�x���� 2016�N�x�ɂ����Đ��ݐ����������鐬���𑱂���Ɨ\�z�����B2017�N�x�ɂ����ẮA����ŗ������グ�O�̋삯���ݎ��v�Ƃ��̔����̉e������ƂƂ��ɁA�i�C�̏z�I�ȓ������f���āA���ݐ������������������x�Ɍ��������A�v���X�������ێ�����Ɨ\�z�����B�v�i2015�N10������W�]���|�[�g�j
�����Ɋ������ɂ�
����W�]���|�[�g�⒘���ȃG�R�m�~�X�g�̌i�C���ʂ��������ɒx���X��������̂́A�������̂��i�C�̐�s�w�W�ł��邱�Ɓi�����悻6������s����ƌ����Ă��܂��j�A�e�퓝�v���o�Ă��画�f����Ƃǂ����Ă��Œᐔ�����͒x��Ă��܂����ƁA���|�[�g���쐬���鐭�{�@�ւ���Z�@�ւ́u��l�̎���v�Ŋy�ϓI�ȃR�����g�ɂȂ炴��Ȃ��A�Ƃ������w�i������悤�Ɏv���܂��B
�����ł���A�e��w�W�ⓝ�v���o�Ă���O�́u�z���́v�������̎��Y�����A�����@������������߂ɋɂ߂ďd�v�Ƃ����܂��B���ɁA�������������n�߂Ă���̂Ɂu���̌o�ς͌��S�v�Ƃ������퓅������ɂ�����A���Y�̔������x������������A5-10�����x�̎����œ��o���σ}�C�i�X3�{�g���b�J�[��n���Z���w���v�b�g���w�����Ă����APER�ȂǂŊ����Ɍ����Ă��i���s�������͂��Ȃ��i�u�C���e���g���b�v�v�ɒ��ӁI�j�Ƃ���������̂�K�v������悤�Ɏv���܂��B
�i�O�̂��ߕt�����܂��ƁA��L�͕M�҂̌l�I�Ȍ����ł���Ae�������g�،��̌����ł͂���܂���B�j
e�������g�،��@�`�[�t�E�I�y���[�e�B���O�E�I�t�B�T�[�@�y����Ёi�ǂ� �܂����j
e�������g�̊֘A�R���e���c
�������e�i�C�[�j�����̌�������
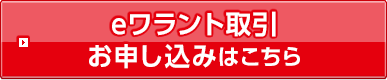

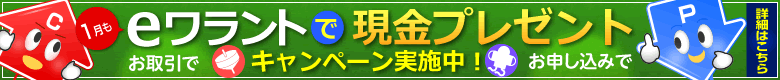
![������ЃN���f�B�Z�]�� ��104�S�ێЍi�ЍԌ��蓯���ʓ���t�j](https://sbisec.akamaized.net/sbisec/images/banner/2024/bnr175_175_bond_japan_8253104.png)