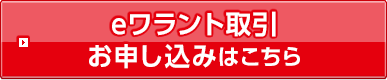世界各国を見渡せば2009年から大相場が始まっていたので、現在は長期調整局面入りしつつある段階と言えそうです。
そういった状況にもかかわらず、「当面の懸念は中国経済の減速と原油価格の低迷だけ」との見方が日本国内には多いようです。
しかし、BIS(国際決済銀行)が公表している国際与信統計を見ると、日本の金融機関もしっかり“お祭り”に参加していて、周囲の状況を見ないで最後まで踊っている様子も窺えます。そうだとすると、年初から続く外国人投資家の脱兎のような日本株売りは、途上国向け与信残高が総額ベースで急減していることも一因かもしれません。
eワラントとは?
そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。
米銀はリーマンショック後に海外与信拡大、邦銀は“ババ”を掴まされたかも
図1は2005年以降の日米欧主要国の金融機関による対外与信残高の推移です。ここでいう与信とは、融資(貸付金)や債券投資にデリバティブなどを含めた信用供与という概念で、広い意味で“銀行融資”と概ね同じとみなすことができます。図を見ると、2008年の世界金融危機(リーマンショック)以降、ドイツ(図中きみどり線)とフランス(図中青線)では、一貫して対外与信残高が減っていることが分かります。これを見る限り、ドイツとフランスの金融機関はまだ不良債権処理を含めたリストラの途上であるといえそうです。
一方、リーマンショック後に急激に対外与信残高を増加させているのが米国の金融機関です(図中緑線)。これはもともと巨大な国内市場があったところがリーマンショック後に国内市場が伸び悩み、海外にビジネス機会を求めた結果と考えられます。英国(図中紫線)はその中間で、ドイツやフランスと同様に2008年以降に対外与信残高を減らしたものの、2010年ごろから再び積極的に外国への与信を増やしています。
日本の金融機関の与信残高(図中赤太線)は欧米とはかなり異質な伸びを見せています。2008年以降の減少はいくらかあったものの、その後も着々と対外与信残高が増えています。さらに、米英独仏のすべてが与信残高を大きく減らしている2014年半ば以降も、せっせと対外与信残高を増やしているのです。日本の金融機関は、欧米の金融機関が対外与信を縮小したことをビジネスチャンスと捉えたようです。しかし、「みんなでダンスを踊っていたら、一人抜け、二人抜けとみんなは家に帰っているのに、ホールの真ん中で一人陽気に踊り続けている」状況ともいえます。杞憂と思いたいところですが、巨大な新興国債権の“ババ”を掴まされた可能性もあります。
図1:主要国銀行の対外与信残高の推移

※BIS国際与信統計データよりeワラント証券が作成
アジア通貨危機では直前から与信残高が減少!
新興国を対象とした先進国からの与信残高がどう変化していたのかを、アジア通貨危機(1997年7月)前後についてみたのが図2です。当時は中国への直接的な与信供与は相対的に少なく、香港(図中紫線)やシンガポール(図中オレンジ線)への与信が飛びぬけていました。これらの資金は、間接的に東南アジア諸国や中国に供給されていたものと考えられます。
アジア通貨危機が始まったタイへの与信残高(図中うす茶線)を見ると、1996年から伸び悩み、1997年後半から激減しています。これに数ヶ月遅れてマレーシア(図中きみどり線)と韓国(図中茶色線)への与信額も急減していました。香港への与信額はアジア危機が始まる2年前の1995年後半から減りはじめ、アジア通貨危機が始まると激減しています。シンガポールと中国(図中赤線)ではやや遅れて与信残高が減り始めましたが、同様にその後数年に亘って日米欧からの与信額が減り続けました。 つまり、経済危機が起こる直前には一部で与信残高の伸びが止まり、経済危機が発生して一旦与信残高が各国で激減し始めると、その傾向が数年間は続くといえそうです。
図2:アジア危機前後の関係国向け与信額の推移

※BIS国際与信統計よりeワラント証券が作成
中国・香港・シンガポール向け与信が2014年半ばから急減!
ここで気になるのが、ちょっと前までもてはやされていた中国、ブラジルなどへの与信残高がこのところどういう動きをしているかという点です。図3は2004年からの主要な新興国への与信残高の推移です。2008年秋の世界金融危機(リーマンショック)直後はどこも与信額が大きく減少しているものの、2009年半ば以降はどこも著しく増加しています。中でも、中国(図中赤線)、香港(図中紫線)、シンガポール(図中オレンジ線)は特に残高の増加が大きく、これらは大部分が中国関連と考えられます。
さらに、これらの残高は2008年以前のピークと2014年の水準を比べれば、中国で約4倍、香港で約2倍、シンガポールで約1.3倍という巨額に達していました。同様にブラジルへの与信額の増加も目覚しく、リーマンショック前の約1.5倍でした(すべて米ドルベース)。
それらがすべて2014年後半から激減しています。特に中国への与信の減少額は大きく、2014年からの1年で既に20%も減少しています。2013年6月のバーナンキショックはこれらの新興国向けの与信額は影響を受けていないようですが、2014年10月の米国の量的緩和政策の終了とは期を同じくしています。
今後の見通しを考えるなら、中国やブラジルでは近年あまりに急激に与信残高が増加していたことから、2008年のような短期回復よりも、1997年のアジア通貨危機後のような数年に亘る与信残高の急減となる可能性が高いように思われます。
図3:2004年以降の途上国向け与信額の推移

※BIS国際与信統計データよりeワラント証券が作成
メガバンクの国際貸出に危険な兆候?
「そうはいっても震源地は中国で日本は関係ないでしょう」
とか
「邦銀は日系企業への貸し出しが主体だから大丈夫なはず」
という声もありそうですが、現実はそう楽観できないようです。
わが国のメガバンクの一角であるみずほFGの開示データによると、国際融資残高は2009年度の9.6兆円から2015年度中間期には2.4倍の23.3兆円に急増しています。総貸出金に占める割合でみるなら、国際融資は2009年度には14.6%であったものが、2015年度中間期にはなんと31.7%に急増しています。これは図1でみたBIS統計と整合性があり、欧米が減らしている対外与信を日本の金融機関がせっせと増やしていることを裏付けています。
また、対外融資が“日系企業”中心かというと、どうもそうとも言い切れないようです。同じく日本を代表するメガバンクの一つであるMUFGの決算説明資料を見ると、中国への貸し出しのうち日系企業は2/3程度のようです。一方、それよりも残高が多い香港への貸し出しでは8割が非日系企業、シンガポールへの貸し出しでも約半分が非日系企業となっています。さらに中国本土の場合は現地企業との合弁が義務付けられていることも少なくないので、“日系企業”といっても東京の本社が経営の支配権を握っているとは限りません。
こうなると、国内のメガバンクが抱える新興国向け(特に中国、香港、シンガポール向け)の与信残高の一部が突然不良債権となることもないとはいえません。今後発表されるBIS統計とメガバンクの決算発表(特に説明会資料)などは要注目です。
投資に活かすには
BIS統計から邦銀が新興国債権の“ババ”を掴まされたと海外投資家が考えたとしたら、マイナス金利政策だけからは説明が付きにくい最近の銀行株の低調さも不自然とはいえません。このシナリオに投資するならメガバンク株のプット、特に決算で巨額の引当金が積まれると仮定して6月満期のメガバンク株プットに投資妙味がありそうです。
逆に本コラムの分析が全くの勘違いで杞憂であり、かつ資本増強のためにメガバンクが増資を行わないのであれば、国内の銀行株を現物で買って数年間保有する戦略が効果的かもしれません。