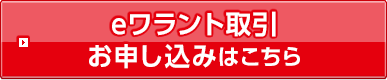2008年の世界金融危機につながったサブプライムローンに起因する米国不動産バブルは、2006年に米国不動産価格が天井をつけていました。しかし、2007年夏の仏大手銀行BNPパリバ系のファンドが破綻した頃までは、まだバブルと認識されていたのではなく、「米国サブプライムローン問題」などとよばれていました。「サブプライムバブル」という呼称が定着するのは、誰の目にもバブル崩壊が明白になった2008年秋以降のようです。
また、2000年が株価の天井となったITバブルは株式中心のバブルでしたが、崩壊する前は「IT革命」ともてはやされていました。それが2000年から2003年に相場が大崩れとなってはじめて、「あっ、あれはITバブルだったんだ」と人々が気付きました。
そうであるなら、2009年3月頃から始まったと考えられる今回の大相場の呼称が「量的緩和バブル」として浸透してきたようであれば、そろそろ大相場は終盤に差し掛かっていると言えるのかもしれません。
eワラントとは?
そもそもワラントってなに?3,000円程の少額から始められる「eワラントの魅力」をご紹介いたします。
10年周期の大相場には、暴落後に“◯×△◯バブル”と呼ばれることになる
日本では、いまだに1980年代末から1990年代初めの「株・不動産バブル」の経験があまりにも強烈なので、「国中が熱狂するようでないとバブルとは呼ばない」ような見方をしている方が多いように見受けられます。このため、だれかが「今はバブルだ。気をつけよう」などというと、「本当のバブルはこんなもんじゃない!」という反応をしがちです。しかし、1989年が株価のピークとなった日本の「株・不動産バブル」は、世界の経済史でも稀に見るほどの超巨大バブルで、「カミカゼバブル」(『バブルの歴史』(エドワード・チャンセラー著)と呼んでいる研究者もいます。
実際にはバブルの周期は7年〜10年周期程度で、概ね設備投資に起因する景気循環(ジュグラー循環)と一致しているようです。また、近年は世界経済・金融のグローバル化で、世界各国の景気循環が同期するようになっています。このため、世界のどこかで巨大バブルが崩壊すると、日本ではちょっとした好景気程度であったとしても、株価や地価の暴落は同じタイミングで大きな波となって押し寄せることになります。このとき、バブル形成と崩壊の震源地となった場所にちなんでバブルの呼称が、事後的かつ自然発生的に決まるようです。だから、2008年の世界金融危機時には米国だけでなく欧州各国で不動産バブルが形成・崩壊したにもかかわらず、まるで米国だけが問題であったかのような「サブプライムバブル」という呼称になっています。
今回は「(米国)量的緩和バブル」であって「アベノミクスバブル」ではない?
私が2015年2月に、拙著「最強の『先読み』投資メソッド」(ビジネス社)で、今回の大相場を「量的緩和バブル」とした時期は、市場参加者の多くが「全くバブル感はない!」という雰囲気でした。それが、2015年3月以降の中国株の急騰急落、2015年8月の人民元ショックあたりから、「中国バブル崩壊が始まったのでは?」という認識に変わりました。
それでも、2015年8月31日付けの本コラムで“「量的緩和バブル」の終わりのはじまり”を書いた時点では、「中国発の局地的かつ一時的な調整」という見方が多かったようです。これを裏付けるように、米国は2015年12月に政策金利引き上げに至っています。
図1は米国のベースマネー(銀行が中央銀行に預けているお金と紙幣・硬貨の合計額)とS&P500の推移です。これをみると、今回の米国株の大相場が2008年の世界金融危機後のFRBによる量的緩和政策によるものであったことが一目瞭然です。特に注意すべき点は2014年にベースマネーの伸びが止まると、S&P500の上昇が止まり、2015年10月からベースマネーが減少すると株価の下落が始まっているという点です。
図2は同様に日本のベースマネーとTOPIXの推移を見たものです。ここでも2012年末にベースマネーの急拡大が始まるのと同時にTOPIXが急騰しています。ここで気にかかるのは、日本のベースマネーが増え続けているのに、株価は2015年7月から下落しているという点です。この原因として考えられるのが、米国のベースマネーの伸び悩み・減少と中国や資源国を中心とした新興国経済の変調です。
図3はユーロ圏のベースマネーとDAX、ユーロ・ストックス50の推移です。ユーロ圏経済は2008年の世界金融危機の後始末が終わらないまま、2010年のギリシャ危機、2011年〜2012年の欧州経済危機を経験しています。このため、2002年から一貫してベースマネーを増やしてきていますが、ユーロ圏全体では、ちょうど日本の1990年代初頭のようなデフレスパイラルに陥りつつあり、「ぬかに釘」の状態です。ユーロ・ストックス50(図中みずいろ線)でみるとユーロ圏全体では低迷が続いている状況と分かります。
一方、“一人勝ち”と言われていたドイツの株価指数であるDAX(図中黒線)をみるなら、ECBの量的緩和政策で株価水準が吹き上げられていたことが分かります。そのDAXも2015年3月からベースマネーが増加しているにも関わらず下げています。その原因は、ユーロ圏全体のデフレ傾向に加えて、日本と同様に米国のベースマネーの伸び悩み・減少と中国や資源国を中心とした新興国経済の変調と考えられます。
図1から図3までで、日米独の株価が中央銀行の量的緩和政策に依存していることから、やはり今回の大相場は「量的緩和バブル」と呼ばれるべきものであるといえそうです。もう少し対象を絞って考えるのであれば、崩壊が始まった原因が米国の量的緩和政策の終焉であり、日欧の中央銀行の量的緩和では支えきれないことから「米国量的緩和バブル」といっても良さそうです。なお、「世界経済の減速は中国経済の不振にあるから中国不動産バブルと呼ぶべきだ」という声もあり得ます。しかし、少なくとも日米独の株価は、各国中央銀行の量的緩和政策で引き上げられてきた経緯からいえば、中国経済だけに責任があるとは言い切れません。
また、日本国内のリベラル系メディアや週刊誌などでは「アベノミクスバブル大崩壊」などという論調も散見されます。しかし、今回も金融緩和相場の総本山が米国であったことや、日本株は他国に4年遅れて2012年末からようやく上昇したにすぎないことから、日本経済だけしかみていない狭小な見解といえるでしょう。逆を言えば、いくら日銀が量的緩和政策でアクセルをふかしても、米国のFRBが金融引き締めでブレーキを踏み続ける限り、株価押し上げは成功しそうもないことになります。
図1:米国のベースマネーとS&P500

※ロイター、FRBデータよりeワラント証券が作成
図2:日本のベースマネーとTOPIX

※ロイター、日銀データよりeワラント証券が作成
図3:ユーロ圏ベースマネーとDAX、ユーロ・ストックス50

※ロイター、ECBデータよりeワラント証券が作成
投資に活かすには
これまでの7年〜10年周期の大相場では、相場が崩壊した後で、「政府の土地政策が失敗」、「金融機関の強欲が悪い」などと魔女狩りが始まるのが“お約束”になっています。その時までには、今回の大相場は“◯◯バブル”と統一された名称で呼ばれるようになることでしょう。現時点では、「量的緩和政策バブル」の他に、「中国不動産バブル」、「新興国バブル」、「世界金融緩和バブル」とさまざまな呼称が乱立しています。
そう考えると、呼称が統一されること(「量的緩和バブル」が筆頭候補)と、バブル崩壊の責任を巡って魔女狩りが始まることの2つが、大相場の大底確認の定性的なシグナルとなりそうです。
これに備えるには、まず、キャッシュポジションを高めつつ、日経平均マイナス3倍トラッカーや株価指数ベアETFに運用資産の10-20%投資してじっと待つ必要がありそうです。その後1-2年程度で、上記の2つのシグナルを確認したら、日経平均プラス5倍トラッカーやブルETF、あるいは長期投資に耐えうる超優良株への個別株投資に切り替えるという投資手法が有効と考えられます。
(念のため付言しますと、上記は筆者の個人的な見解であり、eワラント証券の見解ではありません。)
eワラント証券 チーフ・オペレーティング・オフィサー 土居雅紹(どい まさつぐ)
eワラントの関連コンテンツ
ちょっとe(イー)銘柄の見つけかた
ご注意事項
- eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報はホームページの「
 手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。
手数料及びリスク説明:必ずお読み下さい」をご参照下さい。 - 本資料は情報の提供を目的としており、本資料によって何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社は本資料が正確、完全あるいは/且つ最新のものである事を表明するものではなく、またその責任も負いません。尚、当社及び当社の関連会社、役員、社員その他本資料の作成に携わった関係者が本資料に記された企業の証券または(オプションなどの)派生商品の買い持ちや売り持ち、及び売買を時として行うことがあり得ます。本資料に掲載されている内容の著作権は、原則としてeワラント証券に帰属します。事前に当社の書面による許可なく、本文の一部または全部を第三者へ再配布することを禁じます。
- eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
- ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
- トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
- SBI証券におけるカバードワラント取引手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。
商号等 / eワラント証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会 / 日本証券業協会
提供:eワラント証券