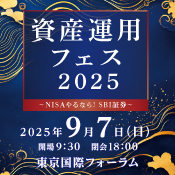間もなく始まる中国の共産党大会をめぐり、習近平総書記の続投や人事の行方に注目が集まっています。最高指導部のメンバーがどう変わるかは、中国の政治・経済にとって重要だからです。今回は、共産党大会の注目点と、共産党大会の「前」と「後」のコロナ政策と株価市場について確認してみたいと思います。
図表1 主な言及銘柄
| 銘柄 | 株価(10/11) | 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|---|---|
| Tracker Fund香港(02800) | 17.49香港ドル | 26.90香港ドル | 17.44香港ドル |
| iS MSCIチャイナ(02801) | 17.66香港ドル | 31.08香港ドル | 17.65香港ドル |
| iS FTSE A50(02823) | 13.38香港ドル | 19.87香港ドル | 13.34香港ドル |
| iS CSI300(02846) | 26.94香港ドル | 41.02香港ドル | 26.80香港ドル |
| iシェアーズ 中国大型株 ETF(FXI) | 24.87米ドル | 42.70米ドル | 25.48米ドル |
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
本レポートを作成する10/11に、筆者は深セン在住の元同僚に、「共産党大会の後、ゼロコロナ政策は緩和されると思う?」と、ショートメッセージを送ってみました。すると、「みんなそう思っている。そうなってほしい。今北京への出張を待っている。」と、返事が返ってきました。
これは、いちサラリーマンである同氏だけの状況とは考えにくく、北京の厳しいゼロコロナ政策によるものと考えられます。つまり、10/16から北京で開催する共産党大会を控え、中国では厳しいゼロコロナ政策が実施されており、一部のビジネス活動にも影響が出ています。
一方、同氏のコメントからは、中国本土ではゼロコロナ政策が共産党大会の「後」に緩和されると「思っている」人も多いということが分かります。つまり、中国のゼロコロナ政策は共産党大会の「前」と「後」で、変わる可能性があることを示唆しています。
共産党大会の「前」と「後」が強く意識されるのは、同大会が最高指導部の人事や政策方針を決める重要な政治イベントであるためです。下記では共産党大会について、10/6付けレポート「中国株 ココがPOINT! 〜10/16から始まる共産党大会、注目点と相場への影響〜」を再掲します。
【共産党大会とは】
共産党大会は、中国共産党全国代表大会の略称で、中国共産党の最高指導部や政策方針を決める最高意思決定機関です。5年に1度秋に、首都北京で開催されます。開催期間はおよそ1週間です。
これまでの慣例ですと、開催初日に共産党総書記による活動報告が行われます。過去5年間の活動を振り返るとともに、今後の政策方針が示されます。そして、開催最終日には中央委員会委員(約200人)が選出されます。この中央委員会による第1回全体会議が共産党大会終了の翌日に開催されます。同会議では、次期の共産党総書記をはじめ、最高指導部の中央政治局委員や中央政治局常務委員のメンバーが選出されます。
図表2 共産党大会の日程等
| 第18回(2012年) | 第19回(2017年) | 第20回(2022年) | |
|---|---|---|---|
| 共産党大会の開催期間 | 11/8(木)- 11/14(水) | 10/18(水)- 10/24(火) | 10/16(日)- 終了日は未公表(※) (※過去と同様に7日間の場合は、10/22(土)に当たる) |
| 活動報告 | 開催初日 | 開催初日 | 開催初日 |
| 中央委員会メンバー(約200人)を選出 | 開催最終日 | 開催最終日 | 開催最終日 |
| 中央委員会第1回全体会議 共産党総書記、中央政治局委員、および中央政治局常務委員を選出 |
11/15に開催 |
10/25に開催 | 慣例だと、共産党大会終了の翌日に開催される予定 |
| 共産党総書記(1名) | 習近平 | 習近平 | |
| 中央政治局常務委員(5-9人、過去2期は7人) | 習近平、李国強、張徳江、兪正声、劉雲山、王岐山、張高麗 | 習近平、李国強、栗戦書、汪洋、王滬寧、趙楽際、韓正 | |
| 中央政治局委員(25名) | 上記の7人に加え、汪洋や韓正など計25名 | 上記の7人に加え、劉鶴や胡春華など計25名 |
※各種資料をもとにSBI証券が作成
【共産党大会の注目点は】
1)最高指導部の人事
共産党大会では中央委員会メンバー(約200人)が選出され、そのメンバーで行われる会議で、次期の最高指導部が選出されます。特に注目されるのは、総書記ですが、習近平氏の続投が市場のコンセンサスとなっています。そのため、今回より注目されるのは、中央政治局常務委員の顔ぶれです。中国の最高指導部に入った人が各中枢部門のトップになるため、それにより中国の政策運営が変わる可能性があります。
たとえば、最高指導部では改革派メンバーが多いのか、それとも成長重視派が多数を占めるのか、あるいはバランス型となるかで、今後数年の中国経済運営方針に影響を与えます。成長重視派となれば、株式市場にとってはプラス材料です。
2)政策方針
最高指導部の人事とともに、共産党大会開催初日に行われる習近平氏の活動報告では、過去5年間を振り返るとともに、今後の政策方針が示される予定です。たとえば、前回2017年に行われた第19回共産党大会で習近平氏は、2012年の第18回共産党大会で提起された「二つの百年奮闘目標」(※)を踏まえ、「2035年の長期目標」を提示しました。
(※一つ目の奮闘目標:中国共産党の結党 100 年となる 2021 年に全面的な小康社会を建設する、二つ目の奮闘目標:中国建国 100 年の 2049 年に富強・民主・文明・調和の社会主義現代化国家を建設する)
「2035年の長期目標」では、二つ目の奮闘目標の達成に向け、2035年までと2035年以降の2段階を設定しました。第1段階の具体的な目標は、1)経済力、科学技術力、総合国力を大幅に引き上げる;2)経済規模と1人当たり所得を新たなレベルに引き上げる;3)コア技術において大きなブレークスルーを実現する;4)イノベーション型国家の上位に入る;5)炭素排出量をピークアウト後、安定的に引き下げるなどが含まれています。
「強い中国」、「イノベーション重視」、「脱炭素」といった目標が目立ちます。これらは、その後の政策運営でも重視している要素となっています。2035年までの目標として提示されているため、これらの重要要素は今回も引き継がれることになると思われます。他方、足元の複雑な世界情勢や経済環境を踏まえ、今後数年という短いスパンで中国当局が何をより重視するのか(たとえば改革か、経済成長か)、それを占う材料が今回提示されるかどうかが注目されます。
短いスパンで注目される政策のうち、ゼロコロナ政策も重要になってくると思います。(1)の冒頭でご紹介しましたように、筆者の元同僚(深セン在住)や周りの人は、共産党大会の「後」にゼロコロナ政策が緩和されるとみています。
その兆候は、北京市マラソン大会の再開からも出ています。毎年秋に開催される北京市マラソン大会は新型コロナの感染拡大による影響で、昨年まで2年連続で休止となりました。ゼロコロナ政策が続いている今年も開催は見送られると思われていました。しかし、マラソン大会の主催者は10/4に予想外に、今年は11/6に開催すると発表しました。首都北京でのマラソン大会の開催は、中央当局の「許可」なしでは実現が難しいと思います。
ただ、今回のマラソン大会は北京市住民に限定しています。その点からすると、ゼロコロナ政策の撤廃を意味するものではなく、一部緩和に過ぎないと言えます。他方、共産党大会の「後」に首都北京でマラソン大会を再開することは、中国がリオープンに向けて動き出そうとしていることを示しています。
国慶節連休の期間中に中国各地で新型コロナの感染者数が増えたことで、中国が再び大規模なロックダウンを実施するのではないかとの懸念が生じました。たとえば、上海市の一部地区は10/10に、感染拡大を防ぐため娯楽施設の一時閉鎖を発表しました。それを受け、上海市のロックダウン懸念が生じました。10/11にブルームバーグTVに出演された上海在住の金融関係者は、全般的に経済活動は続いているとし、今回はロックダウンの可能性は低いとの見方を示しました。
冒頭の筆者の元同僚(深セン在住)は、自宅の隣のマンションがクラスターの発生で「プチロックダウン」状態にありますが、自分が住んでいるマンションはまったく行動規制をしていないと言いました。今年3月の深センロックダウン時の対応に比べると、ずいぶん規制が緩んできた印象です。
香港やマカオの動きからも、中国本土がリオープンに向けて動き出そうとしていることが示唆されています。たとえば、香港は共産党大会の「前」の9月にすでに入境者の隔離期間を3日間から0日間へ短縮しており、共産党大会の「後」は「香港セブンズ」(7人制ラグビーの国際大会)を3年ぶりに再開することを決めました。マカオは9月末に、中国本土からの団体観光客の受け入れを共産党大会の「後」の11月にも再開する方針だと発表しました。
図表3 コロナ政策をめぐる主要都市の動き
| 8月 | 9月 | 10月(共産党大会) | 11月 | |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | マラソン大会が3年ぶりに開催される | |||
| 香港 | 入境者の隔離期間を、7日間から3日間に短縮 | 入境者の隔離期間を、3日間から0日間に短縮 | 「香港セブンズ」(7人制ラグビーの国際大会)が3年ぶりに開催される | |
| マカオ | 中国本土の珠海市からマカオへの陸路ルートで、隔離検疫免除での相互往来を再開 | 9月末に中国本土からの団体観光客の受け入れを11月にも再開する方針を発表 | 中国本土からの団体観光客の受け入れを再開へ |
※各種資料をもとにSBI証券が作成
北京と同様に、香港とマカオのコロナ政策も中央当局の意向が反映されています。中国主要都市の動きからすると、共産党大会の「後」に中国は遅ればせながらリオープンに向けて動き出すこととなりそうです。ただし、これまでの中国の政策運営からすると、リオープンは「漸進的」となりそうです。世界の経済情勢に加え、中国のゼロコロナ政策や不動産市場の軟調が中国経済の減速につながっていることを踏まえると、漸進的とは言え、中国がリオープンに向けて動き出せば、中国経済や株式市場にとってプラス材料となりそうです。
共産党大会の「前」と「後」の株式市場については、短期(1-2週間)と短中期(数カ月)、中長期で過去のパフォーマンスを確認してみたいと思います。
【短期(1-2週間)のパフォーマンス】
過去5回の共産党大会イベント前後のハンセン指数騰落率を確認してみると、開催1週間前が小幅高、開催期間中は小幅安、開催後1週間および2週間は小幅反発となりました。
株価指数のパフォーマンスは、共産党大会だけでなく、その年の相場環境にも影響されるため、まったく同じ傾向をたどるとは限りません。ただし、過去の経験から総じて言えるのは、イベント期間中は「様子見」姿勢が強くなりそうです。イベント通過後(1-2週間)は、共産党指導部の人事や政策方針を確認しながらの動きとなる思われますが、過去5回ではいずれも不透明感の払拭で反発しました。
図表4 過去5回の共産党大会イベント前後(1-2週間)のハンセン指数騰落率
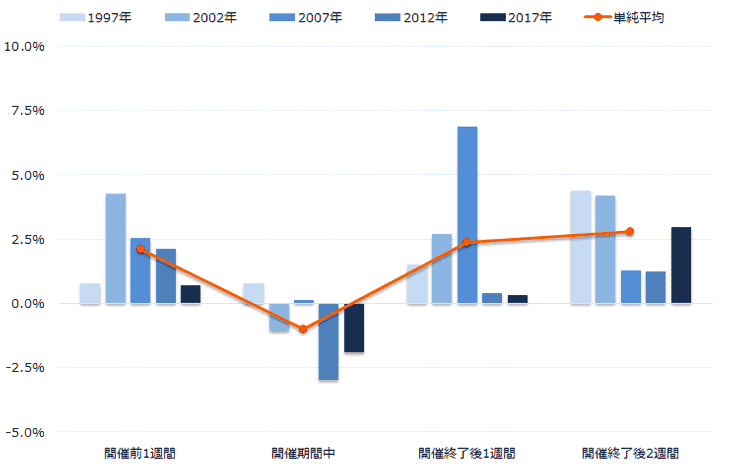
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
【短中期(数カ月)のパフォーマンス】
共産党大会が開催された後、その年の年末までのパフォーマンスを確認してみると、ハンセン指数とMSCI中国指数はいずれも1997年と2002年、2017年は低調で、かつ世界主要株価指数のパフォーマンスを下回りました。特にアジア金融危機の1997年と世界金融危機の2007年の下落が顕著でした。危機を受けた投資資金の引き揚げが背景です。
一方、習近平氏が初めて共産党総書記に就任した2012年と、続投が決まった2017年は、小幅ながらプラスのパフォーマンスとなりました。そのうち、習近平氏が初めて共産党総書記に就任した2012年はMSCI中国指数のパフォーマンスが世界主要株価指数を上回り、続投が決まった2017年はハンセン指数が堅調でした。
図表5 過去5回の共産党大会開催後、年末までのハンセン指数とMSCI中国指数の騰落率
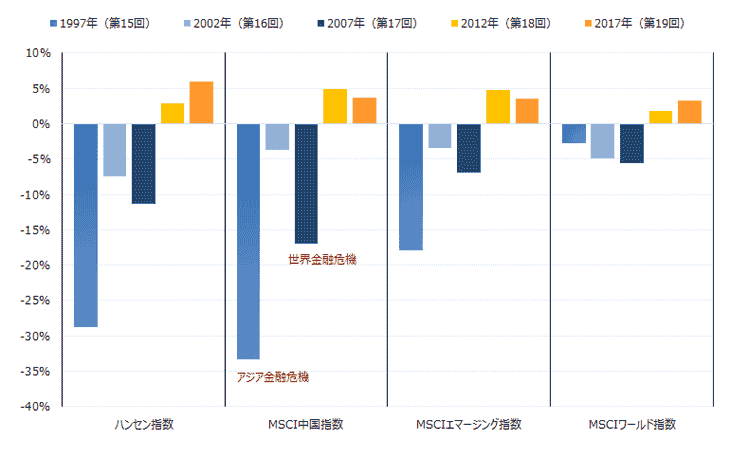
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
【中長期のパフォーマンス】
中長期のパフォーマンスについては、指数の推移で確認してみたいと思います。1997年8月以降のハンセン指数とMSCI中国指数の動きを確認してみると、いずれの指数も大きく変動した時は、共産党大会の開催よりも何らかの危機や摩擦に遭遇した時期でした。
図表6 ハンセン指数とMSCI中国指数の推移(1997年8月から、月次)

※会社資料をもとにSBI証券が作成注:予想PERのデータがなかったため、参考までにPERのデータを使用しました。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
中長期のパフォーマンスにおいては、共産党大会よりも世界金融市場の状況や株価水準(バリュエーション)がより重要な要素となっています。たとえば、MSCI中国指数は2007-2008年の世界金融危機の前に、予想PER(株価収益率)が25.8倍まで急騰した後、金融危機の表面化で予想PERが8.8倍まで低下しました。
なお、MSCI中国指数が底をつける1カ月前の予想PERは10.6倍と、足元(9月末)の10.8倍に近い水準でした。しかし、最後1カ月間のクライマックスで予想PERは10.8倍から8.8倍へ、およそ2割低下しました。その後、MSCI中国指数は反発し、2番底を経て上場局面へ入りました。
足元では、今の世界同時株安を2007-2008年の世界金融危機時と比較する声が増えています。世界同時株安の要因は当時と異なるにせよ、いろいろな要因が絡み合って不透明感が強く、先行きを見通すのが難しい状況にあることは共通していると言えます。
他方、1997年からの中長期的な推移を確認してみると、反発のきっかけはともあれ、大幅な修正を経てバリュエーションが一定水準まで下げると、見直しが入りました。MSCI中国指数の予想PERでみた場合、足元は世界金融危機の底値圏よりはまだ高い水準にあります。ただ、世界金融危機時は最後のクライマックス(短期間)で急落した後、底打ちしました。今回もまったく同じことになるとは限らず、引き続き、警戒が必要でしょう。他方、中長期投資の観点からすると、警戒しつつも時間分散の押し目買いを検討しても良いかもしれません。
免責事項・注意事項
- 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。



 共産党大会の注目点
共産党大会の注目点
 共産党大会の「後」に、「リオープン」あるか
共産党大会の「後」に、「リオープン」あるか
 共産党大会の「前」と「後」の株式市場
共産党大会の「前」と「後」の株式市場