2014年1月以降の約8か月間の変動幅はわずか4円69銭
今年初め頃、昨年10月下旬に97円前後で取引されていたドル円が、昨年末にかけて勢いよく105円まで上昇していた相場展開に、「2014年もドル高円安が進む」と期待を膨らませた人たちが多数いたことが思い出されます。ところが、実際の相場は予想外の展開に。年初から先月(8月)半ば過ぎまで極端に変動幅の小さい相場が続きました。こうした変動幅の小さい相場も、長くて3,4ヵ月程度の期間であれば過去にも幾度となく経験していますが、これだけ長い期間にわたる変動幅の小さい相場は、変動相場制になってからは初めてのはずです。とにかく、1月2日から8月22日までの間、高値105円44銭から安値100円75銭まで僅か4円69銭の変動幅しかなかったのです。
米ドル/円 直近までの値動き
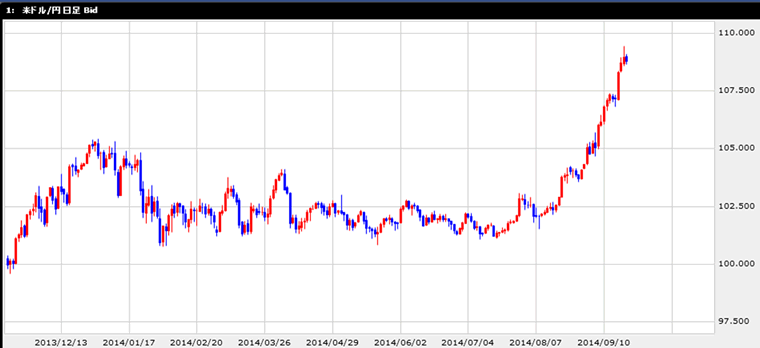
出所:総合分析チャート 日足
実は、2000年代に何度も年間を通して比較的変動幅が小さい年(下表参照)を経験していますが、今年ほど変動幅が小さく期間も長く続いた年はありません。中でも2003年は、年間の変動幅こそ最終的には広がりましたが、1月から6月までに限っては、高値121円47銭、安値115円03銭の変動幅6円44銭という年でした。それでも期間の長さ、変動幅ともに今年の記録には及びません。因みにこの年、7月から年末に向けて円高方向へ13円60銭ほどの変動幅を伴う相場になりました。前年2002年初頭の134円台から徐々に円高が進み、翌年2004年には102円台となっていたように、長期にわたる緩やかな円高相場のどまん中だったことを思えば、2003年下期の動きも当然だったかもしれません。そうした長いトレンドを判断材料にすれば、一昨年秋に始まったアベノミクス相場による超円高から円安に向かっている足元の相場も、8月後半から再度動き始めた円安が年末に向けてさらに進むと判断しても良いのかも知れません。
2000年以降の変動幅が小さい年の比較
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 103.05 | 114.61 | 102.65 | 114.34 | 11.96 |
| 2003年 | 119.86 | 121.44 | 106.91 | 107.11 | 14.53 |
| 2004年 | 106.94 | 114.26 | 102.5 | 102.71 | 11.76 |
| 2006年 | 116.35 | 119.8 | 110.02 | 119.03 | 9.77 |
| 2014年 (8月22日まで) |
105.24 | 105.44 | 100.75 | ? | 4.69 |
作成:SBIリクイディティ・マーケット社
とは言っても、過去の相場の経験則的な理由だけで今年年末に向けての相場を語ってしまうのは、いささか乱暴単純なので、8月半ば過ぎまで続いた変動幅の極端に小さくなった相場の見直しと足元から年末方向へのファンダメンタル面も考えておきたいと思います。
今年の円相場が極端に変動幅が小さくなった理由には、まず順調に景気回復の足取りを確認できると思っていた米経済が、昨年末から春先まで続いた寒波による悪天候で、足踏みどころか第1四半期GDPがマイナス成長にまで落ち込んだことが挙げられます。たとえ米景気の回復は間違いないと思っていても、目の前の指標結果が極端に弱いとなれば、どうしてもドル買いを続けることへの自信が減少、慎重姿勢になってしまったのは無理もないことでした。さらに悪天候の影響は春先までに留まらず、4月以降も暫く余波が続いたことも大きく影響しました。また、このマイナス成長が景気回復を遅らせているとの危惧は、イエレン議長を始めとする連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定にも影を落としたはずです。その後も雇用統計を中心とした米経済指標は、順調に景気の回復を示しているように見えたのですが、FOMCは6月になっても景気の先行きが不透明との見方を示し、市場の投資・投機意欲が次第に小さくなっていったのが実情でした。ポジションの積み上げが小さいままでは、本来インパクトがあるような指標・イベントに際しても反騰、反落といった動きも起きず、ボラティリティーが低下したまま半ば見放されたような相場が今年8月半ばまで続いたわけです。
7月のFOMCでも早期の利上げを示唆するような声明とはならず、この変動幅の小さい相場は8月になっても続いたのですが、遂に8月20日、7月のFOMC議事要旨が発表された頃から相場に変化が起きはじめました。この後、ジャクソンホールでのイエレン議長講演、GDPの予想以上に強い結果などを経て、米金利が堅調になり始めたこともあり、9月のFOMC声明文でも相変わらず「ゼロ金利政策を『相当な期間』維持する」との文言が残ったにも関わらず9月に入り5円以上の円安が進んでいます。米金融当局からの言及はありませんが、市場が早期の利上げを織り込み始めたのです。
今後の見通しは?
今日(9月19日)現在、109円台までドル買いが進んでいる円相場ですが、さすがにドルの上昇が短時間で大幅となっていることから一時的な調整は入るでしょう。ただ、年末に向けてもこのドル買い・円売りの流れは止まりそうもありません。9月のFOMCでは見送られたものの、市場は10月か12月のFOMCで、いよいよ利上げ時期を明確にするはずとの見方が強くなっています。じり高傾向に転じてきた米金利もさらに上昇が鮮明になることが予想されます。欧州中央銀行や日銀には追加緩和の可能性も観測され、対ドルでは対照的な金融政策展望となっています。日本の為替需給もかつてのようなドル余剰構造ではなくなっており、需給面でも急激なドル売りとなる可能性は小さくなっています。ウクライナとロシア、イスラエルとパレスチナ、米国・イスラム国との地政学リスクの急拡大や中国のデフォルトなどという事態さえなければ、ドル買いをメインシナリオとするのが、むしろ一番の安全策と言えそうです。
ドル円相場に影響の大きい年内の注目すべき指標・イベント予定
| 指標・イベント・想定リスク | スケジュール(予定) |
|---|---|
| 米雇用統計 | 10月3日、11月7日、12月5日 |
| 米FOMC | 10月28〜29日、12月16〜17日 |
| 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)ポートフォリオ変更 | 年内 |
| 日銀による追加緩和の可能性 | 年内実施の可能性も浮上 |
| ウクライナとロシアとの紛争、米国の対イスラム国問題などの地政学リスク | - |
| 欧州中央銀行(ECB)のTLTRO | 年内 |
| 米議会中間選挙 | 11月4日 |
| 中国経済の急減速(部分的デフォルトも) | - |






