日米金融政策会合を終えて、今後のポイント
9/5の講演の中で黒田日銀総裁は「マイナス金利の深堀りも、量的緩和の拡大もまだ不十分である」と語ってから、わずか2週間ほどしか経過していない21日(水)の政策会合で日銀は政策目標をこれまでの「量的緩和」から「金利重視型」へ大きく転換しました。
日銀政策会合の決定は難解すぎた!?
今回の政策会合で決定した二つの柱は、以下の通りでした。
(1) 長短金利の操作を行う「イールドカーブ・コントロール」
(2) 物価目標2%を超えるまでマネタリーベースの拡大を継続する「オーバーシュート型コミットメント」
↓
『マイナス金利の深堀りはなし』
『短期金利はマイナス0.1%程度を維持する一方、10年物国債利回りは0%程度で推移するように長期国債の買入れを行う』
決定を受けた市場関係者の第一印象は「難解すぎる!」といったもので、「未だに消化不良」との声も聞かれます。
政策会合の結果を受けて長短金利差により利鞘を稼ぐことができるとの見通しから、21日(水)の日経平均は政策決定前の80円安から400円近く上昇し、315円高で取引を終了したほか、ドル円も102円78銭まで上昇、株高・円安となりました。
しかし、こうした動きは長続きせず、日銀政策会合後の日本時間の深夜に開催されたFOMCの現状維持決定と同時に年内利上げも依然不確実のままになっていたため、ドル円は一時100円10銭まで円高が進みました。
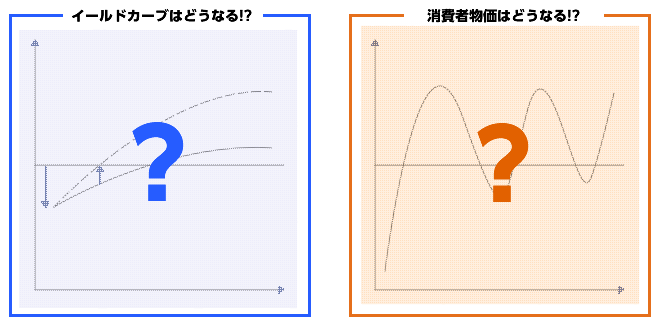
円高進行の背景 5ポイント
円高が進行した背景ですが、まとめると下記の5点が考えられます。
(1)日銀の「量的緩和」に限界を感じ、金融政策の軸足を「金利」に移したことで、日銀が供給する資金量が減少するとの懸念から緩和縮小との見方が出た
(2)日銀が長短金利差の拡大を目指すことで、国内投資家による外債投資から日本国債への資金回帰が起こるとの見方が出た
(3)米FOMCで年内1回の利上げが見込まれたとしても米国経済に切迫した過熱感がない
(4)米国の来年の利上げペース見通しの後退(年3回から年2回へ)、2017年末、2018年末の政策金利見通しが引下がった
(5)日米金利差縮小もしくは金利差拡大は限定的との考えが円高への心理的圧力になった
11月8日米大統領選に向けて・・・TV討論会後の支持率に注意
そして11月8日の米大統領選が米国経済のみならず世界経済や米国の金融政策に影響を及ぼす可能性があるだけにTV討論後の支持率の変化に注意が必要かもしれません。
TV討論会は9月26日(日本時間27日、午前10時)を皮切りに、その後10月9日、19日と3回予定されています。最新の世論調査(日本時間26日午前10時30分現在)ではクリントン候補の支持率が48%に対し、トランプ候補の支持率が44%と依然拮抗、予断を許さない状況が続いています。
TV討論会での注目点は、(1)エネルギー政策(2)ヘルスケア(3)金融規制(4)経済運営(5)税制改革などが争点となるほか、クリントン候補の健康問題や私用メールの公務使用問題に対するトランプ候補の追及があると思われます。その一方でクリントン候補によるトランプ候補への外交・安全保障に対する方針の追及が予想されます。
TV討論会後にトランプ候補への支持率がクリントン候補への支持率を上回ることになれば、トランプ候補がFRBの金融政策への批判を強め、年複数回の監査導入措置などのFRB改革案を主張するかもしれません。その結果、FRBの金融政策の自由度が奪われるとの懸念も出ています。今後のFRBの金融政策の展望が不透明になるとの懸念からドル売りが強まるかもしれません。
さらに保護貿易の意向を示していることから景気にはマイナスに作用、一方で物価上昇という米国経済にはネガティブな影響も懸念されています。
一方で、クリントン候補は2017年度に大型のインフラ投資などを通じて景気刺激策の方針を掲げており、利上げペースに対してプラスに働くかもしれません。
日米の金融政策の行方は12月に持ち越し
今後の日米の金融政策の行方は12月を見据える動きが強まると予想されています。11月のFOMCは大統領選直前であり、昨年12月の利上げと同様に今年も12月のFOMCの行方が注目されそうです。
12月のFOMCで利上げが見送られることになれば、来年以降の利上げのハードルはこれまで以上に高くなってしまい、ドル円も100円割れが定着する懸念も高まるかもしれません。
12月の日米金融政策は9月とは逆にFOMC後に日銀政策会合が開催される日程となっており、FOMCの決定次第では日銀の金融政策が円高阻止に向けてマイナス金利の深堀りや国債買入れ、さらにはETF(上場投資信託)の買入れ枠の増枠などの円高対策を前面に押し出さざるを得ない状況になるかもしれません。
イエレン議長の常套句ともされる「利上げの可能性は経済指標次第」、いずれにしても12月に向けて、今後の米経済指標や7−9月期の企業決算、さらに先行きの企業業績見通しの行方に注意が必要かもしれません。






