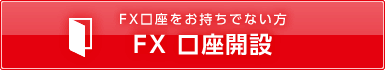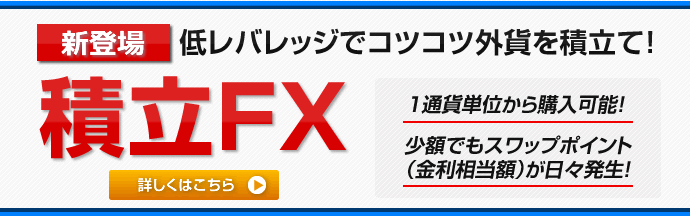ドルの重石となる材料が並んでいるが・・・
11/23(日本時間午前4時)に公表される10月FOMC議事要旨では、12月の追加利上げを完全に織込むと見られていますが、ドル円は先週末のNY市場で111円95銭まで、さらに週明けの東京市場では一時111円89銭まで円高が進んでいます。
先週末、昨年の米大統領選に絡むロシア関連疑惑を巡り「特別検察官がトランプ陣営幹部に召喚状」といった報道に加え、税制改革法案を巡る議会上院での行方に不透明感が出ており、ドルの重石となっていると見られています。また、米国の実質金利の低迷も大きく影響しているように思われます。
また、11/15に発表された米10月消費者物価指数では、変動の激しいエネルギーや食料品を除いたコア指数が前年比+1.8%となりました。
来年2月に退任するイエレンFRB議長の後任となるパウエル理事も、緩やかな金利上昇により金融政策の正常化を継承する方針と見られているものの、シカゴ連銀が「信用」、「リスク」、「レバレッジ」の3つのカテゴリー毎に分類し、総計105の変数を用いて算出される『全米金融環境指数(NFCI)」は先週-0.93まで低下し、金融環境が緩和的水準に置かれていることを物語る結果となりました。
全米金融環境指数(NFCI)

- ※出所:シカゴ連銀
米長期金利が上昇するのか注目!
10/27に発表された米7-9月期GDP速報値は、前期比年率+3.0%と前期(+3.1%)に続いて2四半期連続で3.0%成長を上回ったほか、失業率も4.1%と16年10ヵ月ぶりの低水準まで改善が進んでいます。好調な米国経済に支えられ、企業収益も好調さを継続しており、企業の設備投資も積極的に推し進めることが可能な経済環境にあると言えます。
こうした状況にもかかわらず、FRBの掲げるインフレ率2%の目標には届いていないばかりか、「急速にインフレが加速するような状況にない」との見方が金利上昇にブレーキをかけているようです。
今週公表されるFOMC議事要旨や、来週早々にも公表される感謝祭(23日)後から始まる本格的なクリスマス商戦での個人消費の結果次第で、米長期金利が上昇するのか注目です。
米 債券利回り
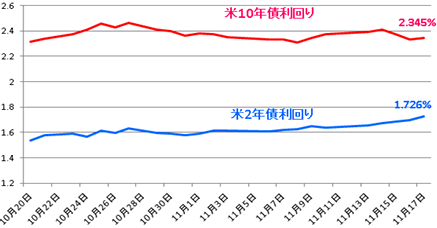
- ※出所:SBIリクイディティ・マーケット社
米債券市場を見ると、2年債利回りが上昇傾向にある一方、10年債利回りは伸び悩んでおり、長短金利差が縮小傾向(長短金利のフラットニング)に進んでいます。
通常、長短金利差の逆転が生じると景気が失速する兆候の一つとされていますが、前述したとおり2四半期連続で3.0%を上回る成長率や歴史的な低失業率、さらに史上最高値圏にあるNYダウをはじめとするNY株価指数を見ると、債券市場(金利の世界)だけが異様に映ります。
単にヘッジファンドの決算に伴うポジション調整の影響に過ぎないのか、あるいは経済指標に表れない消費者心理が予想以上に保守的になっているのか、明確な理由が見えません。
それだけに、11/23の感謝祭明け以降本格化するクリスマス商戦が債券市場の転機につながり、再度債券市場が正常化(フラットニングからスティープニング)に向かうのか、FOMC議事要旨の公表を含めて注目されます。
すなわち、ドル円は111円台後半で底打ちを確認し、年末に向けて円安基調に戻ることができるのか、微妙な局面に差し掛かっているのかもしれません。