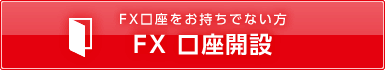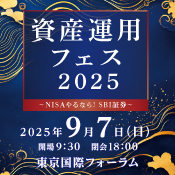米9月雇用統計のポイント
・失業率は48年9ヵ月ぶりの3.7%へ改善、堅調な労働市場を確認
・米10年債利回りは2011年5月以来となる3.246%へ上昇、NY株式市場は調整売り
・就業者数は13.4万人と予想(18.5万人)を下回った一方、直近2ヵ月で8.7万人に上方修正
・ハリケーンの影響による就業不能労働者数が平均の3.5倍、就業環境は良好継続
・製造業の就業者数は前月(0.5万人増)から1.8万人増へ改善
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非農業部門 雇用者数(万人) | 17.5 | 26.8 | 20.8 | 16.5 | 27.0 | 13.4 |
| 失業率(%) | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 時間給賃金 前月比(%) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 時間給賃金 前年比(%) | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
※出所:SBIリクイディティ・マーケット
1960年台後半以来の低失業率が意味するものとは?
9月の非農業部門就業者数は予想(18.5万人増)を下回る13.4万人増に留まったものの、就業者数の伸び悩みには、ハリケーン「フローレンス」による就業不能労働者の増加が影響した可能性が高いと言われています。
一方、失業率は3.7%と予想(3.8%)以上に労働市場の改善が進んでおり、米企業の採用難を示す結果となったと言えそうです。
1960年台のインフレ率を振り返ると、60年台前半こそ低水準の状況が続いていたものの、1960年台半ば以降、賃金と物価が上向きはじめ、インフレ率は1965年終盤の前年比+1.9%から、1969年終盤には前年比+5.9%へ上昇しました。
当時のFRBは、予防的インフレに備えて早期の金融引き締めを行っておらず、急激にインフレ率が上昇した1969年に翌日物金利を6.0%から9.0%へ引き上げました。
こうした対応によって、株式市場は大幅安となり、米国経済はリセッション入りを余儀なくされました。インフレ対応の遅れが景気後退を招く結果となった教訓は、現在のFRBの金融政策に活かされています。市場では来年にかけて現行の利上げペース継続が見込まれ、米長期金利の上昇に影響していると思われます。
また、失業率は昨年9月の4.2%から今年9月の3.7%へ低下、今後一段と低下し、労働市場の逼迫が一段と加速した場合、FRBはどのような対応は講じるのか、FRBが金融引き締めペースを加速させる可能性を考え始める可能性に備える必要があるのかもしれません。
米失業率(%)の推移
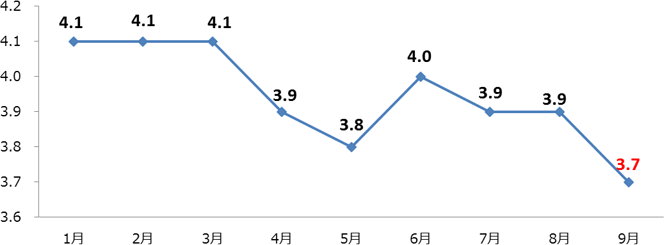
※出所:米労働省
時間給賃金は年末に向けて上昇?
米国経済が好調に推移する中、11月の感謝祭明け以降、クリスマスへの年末商戦に向けて深刻な人手不足が生じる可能性が懸念されています。
こうした動きに備えて、ネット通販最大手のアマゾンでは、11月以降、従業員の最低賃金を持久15ドル(約1,700円)に引き上げることを決定しました。既に雇用している25万人のみならず、年末商戦に向けて新たに短期雇用予定10万人も対象にするとのこと。こうした先手を打つ対応策も、労働市場での企業の採用難を象徴する動きかもしれません。
当然のことながら、人手不足解消のために他の企業も追随すると、全体的な賃金増加につながると予想されます。一部の人材派遣会社では、25セントから1ドルほどの時間給賃金の上昇で、およそ40%の労働者が職を変えてしまうと言われています。
企業の人材確保の動きが加速すると予想される年末に向けて、賃金は一段と上昇する傾向にあると言えそうです。
米時間給賃金 前月比(%) 、 前年比(%)
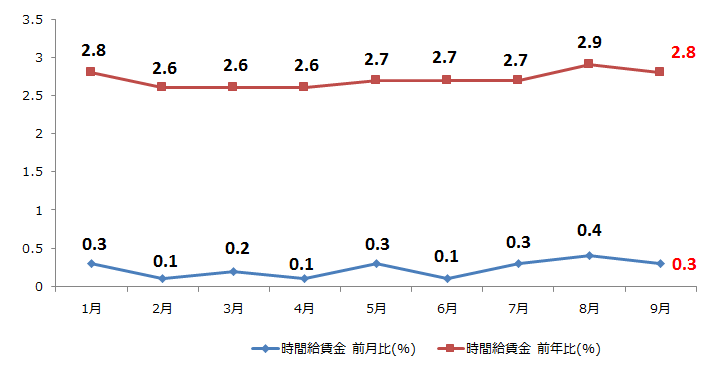
※出所:米労働省
米10年債利回りは3.5%を上回るか!?
米10年債利回りは3.246%へ上昇し、2011年5月以来の高水準となりました。
こうした動きが嫌気され、NY株式市場の強気相場が今後も継続するのか、市場では懸念する見方が聞かれるなど、疑問符が付きはじめたと見られています。
元々、10年債利回りは企業や政府の借入コスト、さらには消費者の住宅や自動車ローンなどのコストを算出するベンチマークの一つとなります。堅調な経済を反映して、NYダウは先週10/3に26,828ドルの史上最高値を更新しました。
しかし、今後も米長期債利回りの上昇が続けば、リスク資産の保有を減らすなどの動きに転じる可能性もあり、行き過ぎた金利上昇が株式市場の調整を招くことで、景気拡大ペースの鈍化につながる可能性も否定できません。
過去のデータを見ると、一般的に米10年債利回りが5.0%を上回ると株式市場の転換点につながると言われてきたものの、量的緩和を含めおよそ10年続いた金融緩和政策の後の金利上昇サイクルは、これまでの事例があてはまりにくく、3.5%が目安になるとの分析も聞かれています。
大手米系証券は、2019年末まであと5回の利上げを実施するとみており、これにあてはめると、米10年債利回りはいずれ3.4%に上昇するとの予想を公表しました。
今週には、米大手金融機関をはじめ7-9月期の企業決算の発表が始まります。減税効果や株式市場上昇による配当増など、個人消費も堅調に推移しており、金利上昇が企業業績に及ぼす影響を見極める段階に入りつつあるのかもしれません。
果たして、今週発表される米消費者物価指数などのインフレ指標によって一段の金利上昇につながるのか、債券市場の動向が注目されます。