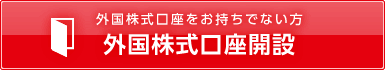マーケット > レポート > 広瀬の外国株式・海外ETFデビュー講座 > イールドカーブについて
イールドカーブについて
イールドカーブについて
2018/12/6
2017年4月17日の「利回り曲線と経済」と題された本コラムの過去記事でイールドカーブ(利回り曲線)について解説しました。
実は今週に入ってアメリカの株式市場ではこのイールドカーブを巡って大騒ぎになっています。それが原因で12月4日(火)の立会ではダウ工業株価平均指数が一時−800ポイントも下げる局面がありました。
そこで急いでイールドカーブの議論を復習する必要があると感じたので、今日はそれについて書きます。
 イールドカーブとは?
イールドカーブとは?
イールドカーブ(Yield curve)は日本語では利回り曲線と訳されます。債券の利回りを、償還期限の長さに応じて、短いものから長いものへとずらりと横一線にならべ、その利回りの点を線でつなげたものがイールドカーブなのです。
少し呑み込みにくいと思いますので、噛み砕いて説明します。
債券には返済期限が早く到来する短期債、何十年も先まで借り手がお金を返さなくて良い長期債など、いろいろな種類があります。
お金を返す期限が到来して、債券の出し手が投資家に現金を渡す行為を償還(しょうかん)と言います。そして償還までの時間をデュレーション(Duration)と言います。
三ヵ月とか六ヶ月という風に、デュレーションが短い債券は短期債と呼ばれ、「準キャッシュ」のように見做されます。
なぜならその債券が発行されてから償還を迎えるまでの期間が短いので債券価格が乱高下することは稀(まれ)ですし、数か月間抱き続けているだけで、銀行預金より少し有利な利回りを得ることが出来るからです。
これに対し10年債とか20年債は長期債と呼ばれます。国の発行する国債なら、10年や20年のうちにその国が消滅するリスクは低いのでよっぽど窮地に立たされた国を除けば元本は返ってくると考えるのが普通です。
しかし発行者が国ではなく企業の場合はどうでしょうか?
企業の場合、不景気のとき業績を大きく落とすところもあるでしょうし、場合によっては倒産するところも出るかもしれません。
つまり10年とか20年という長い期間、そのような相手にお金を貸す(=債券を購入するということはつまりその相手にお金を貸しているのと同じです!)のであれば、それ相応の見返りを貰わないと割に合わないのです。
そのような理由から長期債の利回りは短期債の利回りよりチョッと投資家にとって有利(=つまり利回りが高いということ)になっているのが普通です。
具体的にその様子をイールドカーブで見ることにします。
下は米国財務省証券(トレジャリー)の利回り曲線です。水色は去年の末のイールドカーブです。チャートの左端は3ヵ月物、つまり短期債で、そこから画面の右側へ行くほどデュレーションの長い債券を配置しています。すると水色のイールドカーブは左端が一番低く、そこから右に行くほど高くなっていることが読み取れます。

これが「正規のイールドカーブ」と呼ばれるものです。つまり上で説明した「長期でお金を貸すのならリスクがある。それ応分の高い利回りをもらわないと、割に合わない」という理屈が、このチャートにもちゃんと反映されているというわけです。
 イールドカーブと景気
イールドカーブと景気
長期債はインフレの悪影響を受けやすいです。だから景気が強く、インフレが起きやすい局面では長期債の価格は大きく下落(=その場合利回りは逆に上昇)しやすいです。
つまり好景気の初期から中期にかけては「正規のイールドカーブ」は勾配(こうばい)が急になることが多いのです。
さて、中央銀行は景気が強すぎ、インフレが荒れ狂うと良くないので、ある程度好景気が定着してくるとじわじわ政策金利を引き上げ始めます。実はいま我々が経験しているのは、まさしくそのような金利引締め局面です。
米国の中央銀行は連邦準備制度理事会(FRB)であり、彼らが操作する政策金利はフェデラルファンズ・レート(略してFFレート)です。これは短期の金利です。
いまFRBがFFレートを引き上げるのであれば、上のチャートの左端のスタート地点は、政策金利引上げを反映するカタチで、比較的高い位置からのスタートということになります。それが橙色の線、すなわち12月4日現在の線になります。
<フラットニング(平坦化)>
ここで現在のイールドカーブである橙色の線と1年前のイールドカーブである水色の線を見比べてください。どちらの勾配が急ですか?
これを見ると橙色の線が平べったく「横一線」になっている様子がわかると思います。これがフラットニング(平坦化)と呼ばれる現象です。
いま中央銀行は短期金利をグイッと引き上げてインフレを抑制しようとしているわけだけど、そういう風に金利を引き上げると経済の勢いそのものを殺してしまうリスクがあります。
実際、最近は住宅ローン金利が上昇してしまったため、消費者がマイホームを買う時のローンが昔より組みにくくなってしまいました。
家が買いにくくなるということは住宅が売れなくなることを意味し、それはひいては不景気を招来します。市場が不景気の到来を嗅ぎ付けると、価格変動の大きい10年債などの長期債の価格が上昇、利回りは逆に低下するという現象をもたらします。
つまりその場合、イールドカーブの左端は「↑」の圧力がかかり、イールドカーブの右端は「↓」の圧力がかかるのです。
その結果、イールドカーブの左端のほうがイールドカーブの右端より「上」になる「逆転現象」が起きる場合があります。
この「逆転現象」のことを「インバース(反転)」と言います。
 不景気の前兆
不景気の前兆
さて、イールドカーブが上に書いたようにインバースの状態になったら、それは景気後退の前兆であると言われています。
いまなぜ株式市場がこのイールドカーブの議論で大騒ぎになっているか? と言えば、もう一度橙色の線をよく見て欲しいのですが、すでに3年と5年のところでは「逆転現象」が起きてしまっているからです。
普通、大半の市場参加者はイールドカーブの判定をする際、10年債利回り−2年債利回りがマイナス圏になるかどうか? に注目しています。未だそれはプラスです。
しかし両者の数値は限りなく接近している、言い換えればもうあと少しで景気後退の警告ランプが点灯するところまで来ているということが実感できるわけです。
<まとめ>
債券の利回りを短いものから長いものへ並べ、その利回りを線でつなげたものがイールドカーブです。
イールドカーブがフラットニングすると、それは景気後退の前兆だと言われています。
いまそのイールドカーブは、限りなく「0」、すなわちフラットに近づいています。つまり景気後退がもうすぐそこまで来ようとしているのです。
現在は未だインバース、すなわち逆転した状態ではないので「警告赤ランプ」は点灯していません。でも「黄信号」は灯っていると理解した方がいいでしょう。
著者
広瀬 隆雄(ひろせたかお)
コンテクスチュアル・インベストメンツLLC マネージング・ディレクター
グローバル投資に精通している米国の投資顧問会社コンテクスチュアル・インベストメンツLLCでマネージング・ディレクターとして活躍中。
1982年 慶応大学法学部政治学科卒業。 三洋証券、SGウォーバーグ証券(現UBS証券)を経て、2003年からハンブレクト&クィスト証券(現JPモルガン証券)に在籍。