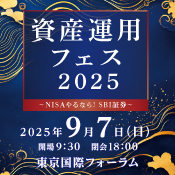FOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表を受けて利上げペースに関する見通しがどのように変化するかは、新興国市場への資金の流れにも影響を与えると考えられます。そこで今回は、新興国株式についての株価動向やバリュエーションをチェックして、物色される可能性について検討しました。
新興国株式のバリュエーションには割安感があり、利上げ予想回数の減少や米国の景況悪化は、株価上昇で割安感が解消される「カタリスト」(きっかけ)になる可能性があると考えられます。ここ4年余り新興国株式のパフォーマンスは不振でしたが、今後はある程度保有しておくべきかもしれません。
新興国株式に広く投資するには、ETFが便利です。ただ、一般に使われる「新興国株式指数」は、国別組入トップが中国です。同国の景気動向、株価動向はまだ安定を欠くことから、新興国の国を選別して投資することも考えられるでしょう。GDP成長率が堅調な国が多く、株価動向にも安定感があり、グローバルな機関投資家の注目も高まりつつある、東南アジアに投資妙味があると見られます。
図表1:新興国株式のETF
| 銘柄 | 株価(3/14) | 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|---|---|
| (新興国株式ETF) | |||
| iシェアーズ MSCI エマージング ETF(EEM) | 32.94ドル | 44.19ドル | 27.61ドル |
| バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO) | 33.42ドル | 45.08ドル | 27.98ドル |
| SPDR S&P 新興国株式 ETF(GMM) | 53.18ドル | 70.41ドル | 44.81ドル |
| ウィズダムツリーエマージングハイディビF(DEM) | 33.94ドル | 48.56ドル | 27.15ドル |
| Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF(EDC) | 11.72ドル | 31.41ドル | 7.11ドル |
| (新興国の個別ETF) | |||
| iシェアーズ MSCI インドネシア ETF(EIDO) | 23.89ドル | 28.17ドル | 16.52ドル |
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF(EPHE) | 35.29ドル | 43.09ドル | 28.98ドル |
| iシェアーズ MSCI タイ・キャップト ETF(THD) | 67.35ドル | 84.47ドル | 54.94ドル |
| マーケット ベクトル ベトナム ETF(VNM) | 14.20ドル | 19.64ドル | 12.34ドル |
※当社WEBサイトを通じてSBI証券が作成
|
|
劣後トレンドながら割安感のある新興国株式 |
3/16(水)のFOMC(米連邦公開市場委員会)を受けて利上げペースに関する見通しがどのように変化しているかは、新興国市場への資金の流れにも影響を与えると考えられます。
そこで今回は、新興国株式について株価やバリュエーションがどのような位置にあるか確認して、今後物色される可能性について検討しました。
まず株価の動向ですが、世界の株式を先進国株式(米欧日など)と新興国株式(中国、インド、ブラジルなど)の2グループに分けて比較したものが図表2になります。
12年からの4年余り新興国株式は先進国株式に劣後してきたことがわかります。日本から外国株に投資する場合、これまでは先進国の米国株を中心に投資していればよく、新興国株式は保有しなくてもよかったと言えるでしょう。
ただ、新興国株式のPERは12.0倍と先進国株式PERの16.4倍に対して割安となっています(図表3)。新興国株価指数のPERが先進国株価指数の約7掛けという関係は14年以来安定していますが、格差が拡大する前の11年は9掛け程度でした。
割安感が解消されるための「カタリスト」(きっかけ)があれば、ある程度格差が修正される可能性があるでしょう。
図表2:パフォーマンスの劣後傾向が続く新興国株価指数
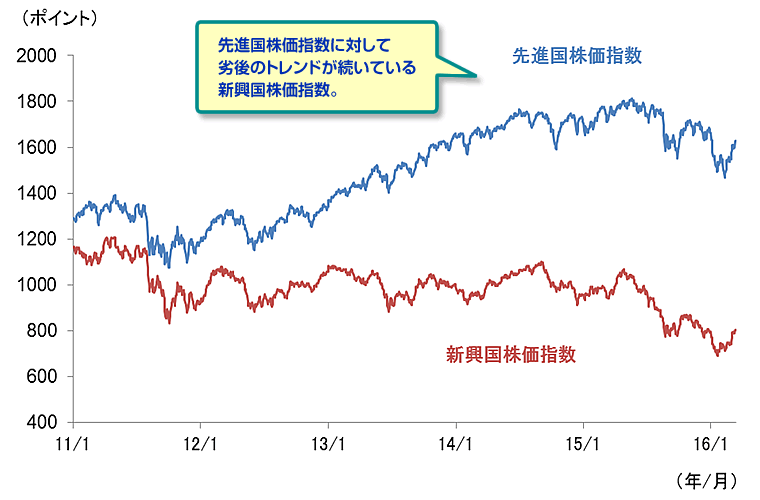
- 注:先進国株価指数はMSCIの先進国株価指数(MXWO)、新興国株価指数は、MSCIの新興国株価指数(MXEF)によります。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
図表3:新興国株式指数の予想PERには割安感があるが・・・
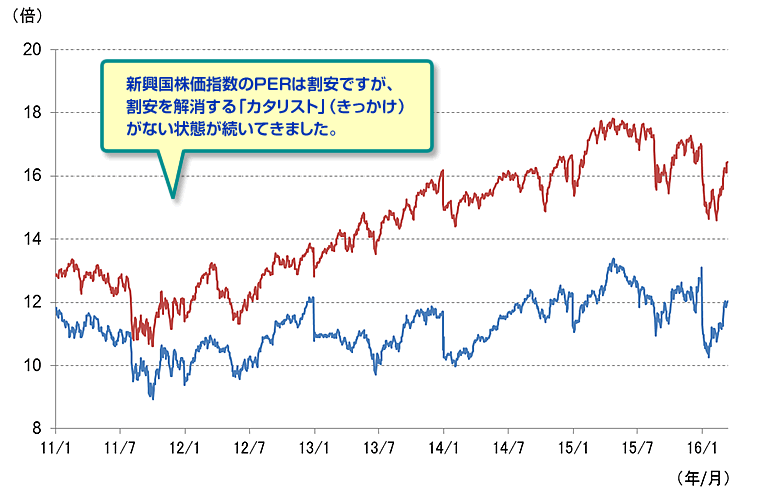
- 注:Bloombergの予想EPSに基づく予想PERです。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
|
|
利上げ動向と米国経済の減速が割安解消の「カタリスト」に? |
新興国株式のバリュエーションの割安が解消されるための「カタリスト」(きっかけ)として、以下の2点に注目できるでしょう。
(1)FRB(米連邦準備制度理事会)による利上げ回数の減少
(2)米国経済の減速
(1)については、昨年12月のFOMCで参加メンバーが予想する16年末の政策金利中央値は、4回の利上げに相当する1.375%でした。その後景況の悪化を受けて3月FOMCでの利上げ見送りが市場コンセンサスとなり、参加メンバーの政策金利予想も1.375%から下がっていると見込まれています。
米国の利上げが意識される中で昨年は新興国株式が大きくアンダーパフォームしました。一方、昨年12月の利上げは意識されていた悪材料の顕在化と言え、さらに、米国経済の減速を受けて今年の利上げ回数が低下するとなると、新興国株式の見直しに繋がる可能性がありそうです。
(2)については、先進国株式が新興国株式のパフォーマンスを上回ってきた要因の一つは、先進国株式の約6割のウェイトを占める米国の内需が堅調であったことと考えられます。
しかし、図表4のように昨年末からISM非製造業景況指数が悪化したことで米国の内需景気に対する懸念が広がりました。指数の水準はまだ高いためリセッションを懸念するほどではないものの、米国経済が減速傾向にあるのは間違いないと見られます。バリュエーション格差を埋める要因になる可能性があるでしょう。
これまで4年にわたってアンダーパフォームし、バリュエーションも低い、新興国株式への物色が高まるカタリストになる可能性が考えられるでしょう。
実際3月(14日時点で)の新興国株式ETFには久しぶりの資金流入が見られています。14年後半から15年にかけて安定した資金流出となっていましたが、上記のようなカタリストを背景に、資金流入の定着が期待されるのではないでしょうか。
新興国株式は、過去4年余りについて言えば保有する必要はなかったと言えますが、今後はどうでしょうか?国際分散投資を考える場合には、ある程度保有しておいたほうが良いのではないでしょうか。
図表4:米国の内需景気に陰り
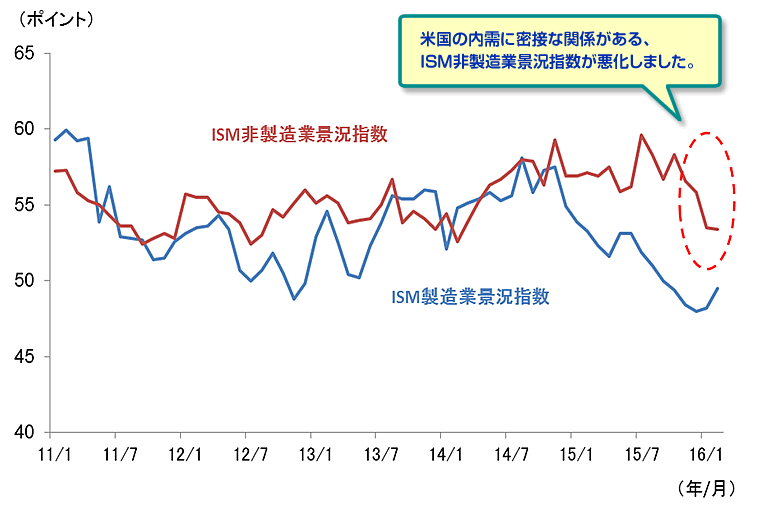
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
図表5:新興国株式ETFに久しぶりの資金流入!!
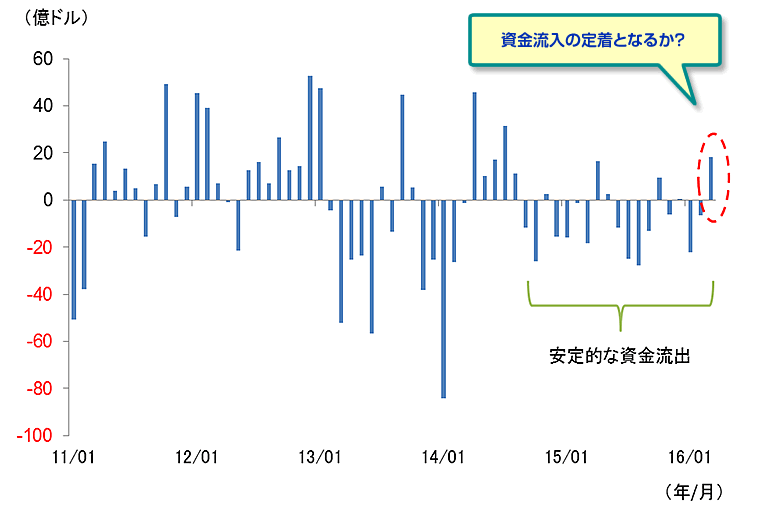
- 注:米国上場の新興国株式ETFで出来高が多い「iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF」と「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF」の資金フローの月次推移です。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
図表6:足元の新興国株式の優位は続くか?
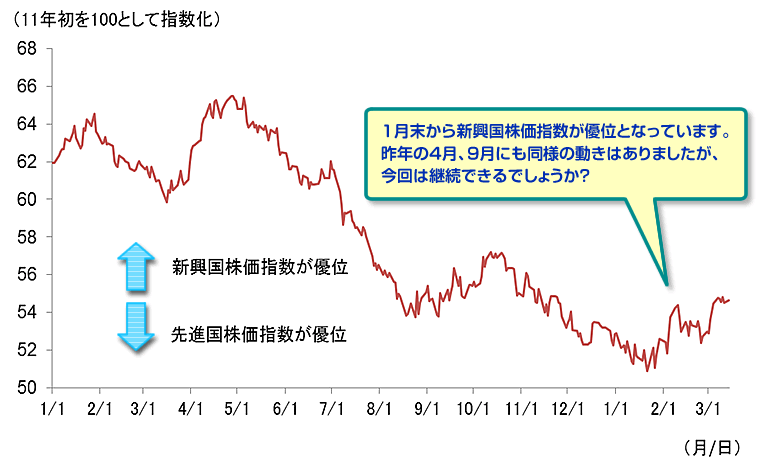
- 注:図表2で取り上げた指数について、「新興国株価指数」÷「先進国株価指数」を計算して、11年初を100として指数化した相対株価です。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
|
|
新興国株式への投資を考える |
新興国に投資する場合に、新興国株式を幅広く網羅する新興国株式ETFが利用できます。
市場での出来高が多い代表的なものには、「iシェアーズ MSCI エマージング ETF(EEM)」 、「バンガード FTSEエマージングマーケッツETF(VWO)」 があります。
これらETFについて、投資対象がどうなっているかを見たのが、図表7です。韓国が入るか否かに違いはあるものの、保有比率の4分の1を超えて最大であるのが中国株であることは変わりません。
中国株については、景気動向は月次指標を見るとやや下振れリスクもあり、株価動向も相対的に弱い状況が続いているため、当面中国は避けたいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
その場合には新興国から国を選んで投資することも考えられます。比較的高いGDP成長を実現している国が多く、株価の動向も市場平均を上回って堅調なものが多くなっています(図表8)。
成長回復と物価安定を背景にグローバルに機関投資家の注目が高まっているインドネシア、人口増加と英語が得意なことを武器に成長の期待が大きいフィリピン、政治の安定で国内経済が回復に向かいつつあるタイ、また、規制緩和やインフラ整備の効果が期待され、さらに、TPPが発効したときに恩恵が大きいベトナムなどに注目できるでしょう。
これら市場の詳細については、以下もご参照ください。
・16年3/2掲載の「成長回復、物価安定で投資チャンスを迎えるインドネシア」
・16年1/27掲載の「“波乱”後の投資先は?高成長のフィリピン、ベトナム、回復のタイに注目!!」
・15年11/19掲載の「ベトナム株式を始めませんか!?TPP、規制緩和、「つばさ橋」の開通で盛り上がるベトナム経済」
図表7:代表的な新興国株式ETFの国別保有状況
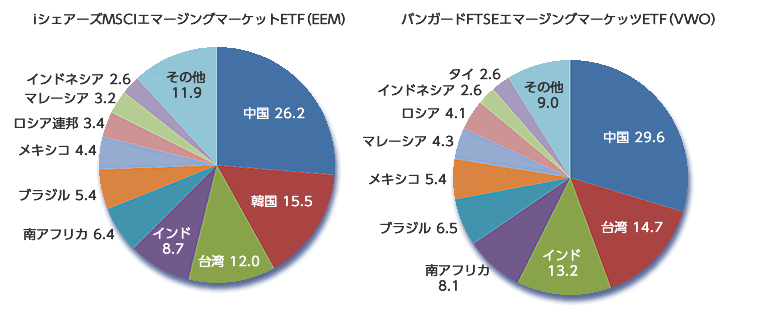
- 注:2015/12/31時点。
- ※ブラックロック社、バンガード社の資料をもとにSBI証券が作成
図表8:注目新興国の株価騰落と投資指標
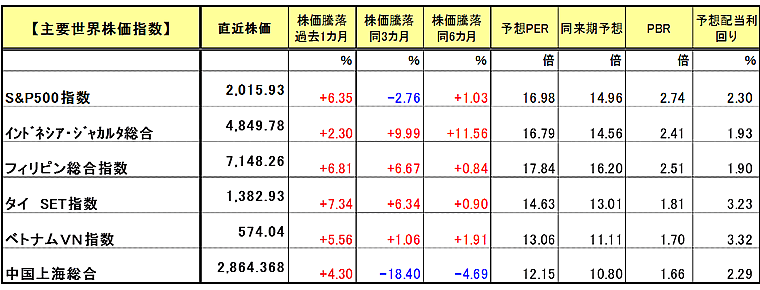
- 注:直近株価は3/15です。
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成成
※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。